このページ
究極のシステム - 第8章
その後
デイビッドは寝返りを打ち、電話に出た。ようやく眠りに落ちたばかりだったので、呼び出し音は少々うっとうしいものだった。電話の向こうからはネイト・フレイザーが出て、「デイビッド、レイトチェックアウトをお願いするはずだ。たいていはイエスと返事が来るはずだ…でも、勝手に決めつけるのは失礼だ。とにかく、もう一泊部屋を借りて、ビュッフェももう少し食べたいなら、手配できると思うよ」と言った。
この時点でデイビッドはすっかり混乱していた。まだ8時なのに、なぜレイトチェックアウトを頼んだだけで叱責されるのか理解できなかった。彼は寝返りを打ち、時計を見た。12時45分!仕事に行かなければならない時間まであと15分しかない。うとうとしていたのではなく、実際には数時間寝ていたに違いない。ようやく周囲の状況とネイトからの電話の理由に慣れ、彼はこう答えた。「うーん…いや、それはできないんです。今日は仕事があるんです。15分かそれ以下でここを出ます。ご迷惑をおかけして申し訳ありません。」
ネイトは明るくこう答えました。「全然問題ありません。何か必要なことがあればいつでも電話してください。」
デビッドは、この発言について深く考えずにこう言った。「実は、仕事場まで車で送ってもらいたいんです。えーと、昨晩、車がエンジンがかからなかったので、今日もエンジンが掛かるかどうか分からないんです。」

ネイトは、実はデイビッドの「車」がデイビッドの空想の産物だと確信していたが、そう断言したくはなかった。「デイビッド、正直に言うと、それはちょっと気が進まないんだ。セダンで職場まで送ってもらうことも考えたけど、今まさに空港に向かっているところなんだ。」
デイビッドはセダンが戻ってくるまで待つことを申し出る可能性を実際に検討したが、ネイトにとってはそうしなかったのが幸いだった。セダンは実際には出動していなかったからだ。デイビッドは運転手に職場まで乗せてもらうほどの実力者ではなかった。それに、カジノから食料品店の職場まで比較的低額の客を乗せるためだけでなく、セダンを出したことが上層部に知れ渡ったら、どれほど叱責されるか想像もつかなかった。最近、デイビッドは相当な額の現金をバイイン(そして損失を出しながら)していたので、ホストを雇えることさえほとんど正当化できないだろう。
デイビッドはついにこう答えた。「大丈夫、間に合うはずだ」。ネイトにとっては、デイビッドが遅れるかどうかは、少なくとも彼が仕事を失わない限り、大した問題ではなかった。それでもデイビッドは、少しでも面目を保つ必要があると感じていた。
デイビッドは状況をよく考え、まずはA Penny Savedに電話し、上司であるデリ・マネージャーのニコラス・アリソンに遅れることを伝えることにした。カスタマーサービスに電話がかかり、デリに転送された。3回目の呼び出し音でニコラスが電話に出た。「A Penny Savedのデリにお電話いただきありがとうございます。ニコラスです。何かお探しですか?」
デイビッドは、自分がしなければならないことに気を引き締めた。ニコラスに電話して尋ねるのが正しい行動ではあったが、本当は係員の誰かが出て、伝言を伝えてくれることを願っていた。しかし、その時、どうせ後でニコラスとやりとりすることになるとほぼ確信していたことに気づいた。「アリソンさん」と彼は切り出した。「あの、車がエンジンがかからなくて、今日は仕事場まで歩いて行かないといけないんです。乗り合わせてくれる人が見つからないんです。3時までには着けると思いますよ」
ニコラス・アリソンは状況を少し考えて、高速道路からデイビッドが店に向かって歩いてくるのを一度か二度見たことがあるのに、デイビッドが車を持っているかどうか確信が持てない、もし持っていないなら、なぜ遅刻の理由について嘘をつくのか、と考えた。嘘をつかれた可能性は高いが、それでもアリソンは、本に書かれているように遅刻は遅刻であり、理由は関係ない、と判断し、「わかった。とにかくできるだけ早く来てくれ」と言った。これはあなたの出席ボーナスと何か関係があるのでしょうか?」
デイビッドは困惑しました。「どういう意味ですか?」
「こういうことは以前にも見てきました。だからこそ、出席は常に義務であり、インセンティブを与えるべきではないのです」とニックは切り出した。「出席ボーナスの支給対象となる時期には皆勤賞与をもらっている人が、一度皆勤賞与をもらってしまうと、あっという間に出席率がガタ落ちしてしまう。ここでこんなことが起きていないことを願います」
まったく、なんてこった、とデイビッドは心底腹立たしく思った。まず、皆勤賞与を四半期ごとに支給して、常にインセンティブを与えておけばいいのに、と。次に、デイビッドは思った。「こんな遅刻は初めてなのに、一体どうしてこんなことがパターンになるんだ?」
デイビッドは、そのどちらかを指摘する代わりに、「ここではそんなことは起きていません。3時までにそこに行きます」と答えました。

デイビッドは、ゴールデン・グースをチェックアウトする前にシャワーを浴びるべきか、少し迷った。何をしても仕事に着く頃には汗だくになるだろうが、シャワーを浴びれば少なくとも少しは臭いが和らぐかもしれない。おそらく人生で一番手早くシャワーを浴び、前日に着ていた服を着た。仕事着は着たくなかった。仕事に着く頃には汗だくになるだろうが、少なくともほとんど乾いているはずだからだ。
デイビッドは「A Penny Saved」のバッグを二つ抱えてエレベーターに急いだ。一つは昨日カジノへ歩いていく際に着ていた汚れた服を入れるバッグ、もう一つは仕事着を入れるバッグだ。いつもよりずっと長く感じられたが、エレベーターは彼の階に到着し、カジノ階へと降りていった。ホテルのフロントデスクへ行き、問題なくチェックアウトした。その後、テーブルゲームに一番近い出口から出ることにした。カジノに出入りする側道は、わずか数フィートの違いではあったが、厳密に言えば正面玄関よりも食料品店に少し近かったからだ。
テーブルゲームエリアを通り過ぎようとした時、サミーがその日は早くからクラップスのテーブルでゲームをしていたことに気づいた。予想以上に大きな声で、サミー以外の20人ほどが振り向くほどだった。デイビッドは「やあ、サミー、おはよう!」と声をかけた。
「そうおっしゃるなら」とサミーは答えました。「買い物袋は何のためにあるんですか?現金を全部入れておくためですか?」
財布の中身を思い浮かべながら、デイビッドは顔が青ざめた。「いや、それはまた別の日に取っておく。なあ、これは大変なことになるな。車が動かないんだ。仕事場まで乗せてもらえないか」

サミーは(正しく)デイビッドには車なんてないんじゃないかと疑っていたが、それでもデイビッドにちょっとした親切をしない理由にはならなかった。「ああ、大丈夫だよ。どうせ負けるんだから。この子にこのロールを終わらせてくれれば、出発するよ。」
子供はデイビッドが急いでいることを知っていたに違いない、なぜなら彼はたった 2 回の投げですぐに 7 を出したからだ。
「あれを見たか?」サミーは尋ねた。「あの子は、君が仕事に取り掛かる必要があることを知っていたに違いない、だって、すぐに7点を投げたんだぞ?」
デイビッドは微笑み返した。「確かにね。ところで、乗せてもらう代わりに何か差し上げましょうか?」デイビッドは、サミーが自分が提示したゼロではない金額が、デイビッドが持っていないゼロではない金額と全く同じであることを悟らないようにと、そう尋ねたのだ。要するに彼はブラフをかけたのだが、少しでも面目を保とうとしたのだ。
何も言わなかったにもかかわらず、サミーはその日もいつもの探偵ぶりを見せた。昨晩の暴行のせいで、デイビッドはおそらく何も持っていないか、ほとんど持っていないのではないかと(これもまた正しかった)疑念を抱いたのだ。サミーは考えた。だって、デイビッドはデリで働いているんだから、そんなに儲かるはずがないじゃないか、と。デイビッドはほっとした。サミーはデイビッドを辱めるつもりなどなかった。それに、そもそもデイビッドは金なんて欲しくないと思っていたのだ。「いいえ」と彼は答えた。「あなたはおそらくいつか私に同じような頼み事をしてくれるでしょう。たとえその日が来なかったとしても、あなたは喜んでそうしてくれると私は知っています。」
「もちろんです」とデイビッドは答えた。「機会があれば恩返しをしないなんて、私には考えられません」
_________________________________________________________________________________
サミーにとって、30年もののマーキュリー・グランドマーキス以上に誇りとなるものはないと誰もが信じたがるだろう。それは事実だからだ。デイビッドの心は、サミーとこの5分間、車について一方的に交わしてきた会話から、ふと離れていった。
「…お店、カジノ、もちろん教会。教会にはもっと頻繁に行くべきです。他の場所にはほとんど連れて行かなくて、週に100マイルくらいしか連れて行かないんです。」
デイヴィッドはぼんやりと尋ねた。「誰にですか?」
「車だよ」とサミーは答えた。デイビッドにただで乗せているのに、デイビッドは会話にほとんど耳を傾ける余裕がないという事実に、サミーは少々苛立たしく感じずにはいられなかった。「長距離の旅行には乗らないし」と彼は続けた。「それに、ずっとガレージにしまってあるんだ。買った時と同じくらい、今もきれいな状態だと思うんだけどね」

「美しい車ですね」とデイビッドさんは言った。
「その通りだ」とサミーは同意した。「彼女が私より長生きしても、少しも驚かないよ。少なくとも、手が許す限りは、今でもオイル交換は全部自分でやっている。もう10年近く、関節炎が断続的に続いているんだ。」
二人は、道路脇に立って「チアリーダー洗車場、左折」と書かれたプラカードを持った女子高生とすれ違った。サミーは「でも、たまには他の人に彼女に触れさせてあげたいと思うこともあるよ」とつぶやいた。
デイビッドは、前の晩にひどい殴打を受けて以来感じていたすべての感情に反して、くすくす笑った。「君は手に負えないね」と彼は言った。「彼女が合法だと思ってるのか?」
彼にとって、それはそれほど重要なことではなかった。特に、どうせ学齢期の女の子を惹きつけることはまずないだろうから。だが、サミーは、少しは面目を保ちたかった。「おいおい、彼女は高校生みたいだったぞ!」
デイビッドはあの女や車のことなど気にしていなかった。前の晩に自分が犯したあらゆる過ちが頭の中を彷徨っていた。犯した過ちのリストが頭の中で次々と積み重なっていき、皮肉なことに、ほぼ全財産を投じて期待値がマイナスのゲームをしていたことは、自分が犯した過ちのリストの中には全く入っていなかった。
デイビッドは頭を左右に振りながら周囲を見回した。ただで乗せてもらえても、ずぶ濡れで職場に着くわけにはいかないので文句は言えないが、サミーが常に制限速度より15マイルも遅い速度で運転していることはデイビッドにも分かっていた。何台もの車が轟音を立てて彼らの横を通り過ぎ、そのうち数台はサミーにクラクションを鳴らした。サミーも親切に手を振り返した。デイビッドは、サミーに乗れば、歩いて職場に着くよりどれだけ早く着けるのだろうと、ぼんやりと考えていた。
サミーの運転の遅さに少しイライラしていたという点を除けば、デイビッドは文字通り、心が空っぽになったように感じていた。胸と頭の両方に、しつこい空虚感を感じ、ほんの数日前から感覚が著しく鈍くなっているように感じた。もう一度辺りを見回すと、まるで目が捉えている映像に合わせて設定されたテレビを見ているかのようだった。まるでスクリーンを通して世界を見ているかのようだった。積極的な参加者というよりは、傍観者のような感覚だった。

彼は自分のふっくらとした手を見て、それから片方の脚に当ててみた。何か…何かを感じるだろうかと。太ももに圧力をかけていること、そして手に圧力がかかっているのを感じながらも、どこかひどく鈍く、非現実的な感覚があった。唯一、確かな感触があるとすれば、それは胃がむずむずする感覚だった。空腹だったが、どうすることもできない。家に帰るまでお腹を空かせていなければならないが、家に帰ってからも、今後 3 日間、昼食として職場に持っていけるものがあるかどうかわからなかった。
「しまった」とデイビッドは言った。「申し訳ないが、君はちょうど店を通り過ぎたばかりだ!」
サミーは右を見て、自分が曲がり角を通り過ぎたことに気づいた。またグランド・マーキスの歴史について語り始め、デイビッドと同じように、現実から少し乖離した状態になっていた…もっとも、理由は大きく異なっていたが。Uターンしても全く問題なかったかもしれないが、反対方向から車が来ていなかったので、サミーは4分の1マイルほど先のガソリンスタンドをUターンの拠点として、そこへ向かうことにした。
サミーは店の正面玄関に車を停めたが、悩んだ末、駐車場の奥に停めることにした。「気にしないでほしいんだけど」と彼はデイビッドに説明した。「でも、せっかく来たんだから、これから数日分の買い物を済ませておこうかな」
サミーはシャツのポケットから「ゴールデン・グース」のチップスを取り出し、おそらく合計100ドル強だっただろうとダッシュボードに置いた。デイビッドは驚いて言った。「そのまま置いていくの!?」
「もちろんよ」とサミーは答えた。「車には鍵をかけるし、ここはとても安全な町だし、カジノのチップを盗もうと誰かが押し入ってくるとは思えないわ」
デイビッドはサミーと一緒に店に入ろうかと思ったが、すぐに引き返して実際にそうしてしまった。もちろん、デイビッドは子供の頃から何も盗んだことがなく、そもそも窓ガラスを割るほどの力があるかどうかも自信がなかったのだ…。
デイビッドは首を横に振り、車に乗せてくれたばかりのサミーから、いや、他の誰かから盗むなんて、全く馬鹿げた考えだと一蹴した。そんな考えが頭に浮かんだこと自体に、驚きを隠せなかった。大金ではないとはいえ、間違いなく刑務所行きになるだろうし、誰かの車に侵入しようとしているところを目撃する目撃者もいくらでもいるだろう。しかも、そこは彼の職場なのだ!
デイビッドはサミーと一緒に歩いて行き、もう一度乗せてくれたことに感謝し、出勤簿に記録しに行きました。
____________________________________________________________________________

デイビッドは、ニコラス・アリソンに電話して話したにもかかわらず、その日の出勤記録を打刻するにはオフィスから優先承認を得なければならないことを一瞬忘れていた。彼はジェシカのところへ行き、明るい茶色の髪と緑の目をした20代後半の女性に話しかけた。彼女もデイビッドと交際しているらしい。彼女はマネージャーのカードをスワイプし、デイビッドは出勤記録を打刻することができた。
デイビッドがデリに戻ると、すぐにニコラス・アリソンが声をかけてきた。「デイビッド・ランドストロム」と彼は優しく声をかけた。「今日はお会いできて光栄です」 アリソンは時計を見て、ちょうど1時半過ぎであることに気づいた。「早いですね。まあ、遅いですが、思っていたほどではありませんね。乗り物は見つかったんですか?」
「そうしました」とデイビッドさんは言いました。「それは素晴らしいことです。ここに着く頃には汗でびっしょりになっていたでしょうから。」
「外見と言えば」とアリソンは話し始めた。「今日は何を仕事に着ていくことにしたの?『ドッグ・ポンド』って、『A Penny Saved』って何のことを表しているのかしら?」
デイビッドは、2ヶ月前にグッドウィルで買ったTシャツの一枚を見下ろした。それは、自分に合う数少ないTシャツの一つだったからだ。「ああ、ごめんなさい」デイビッドは説明のために買い物袋の一つを掲げた。「車に乗せてもらうとは思わなかった。仕事着はここにあるんだ!」
ニコラス・アリソンはデイビッドに向かって左の眉を上げた。「まだ作業服を着ていないということは、まだ出勤していないということでしょうか?」
デイビッドは心の中でうめき声をあげ、信じていない神へと視線を上げた。その日はますます悪化し、デイビッドは病欠にしようかとも一瞬考えたが、特に病気だと言えるような病気はなかった。「いや」デイビッドは落胆して答えた。「もう出勤したから、できるだけ早くこれを着るよ」「
デイビッドは、想像上の恋人ジェシカを小声で罵りながらトイレに向かい、心の中で呟いた。「あの女は、せめて仕事着を着ていないって言ってくれればよかったのに。制服を着ずに出勤させてくれたのも、同じくらい彼女の責任じゃないか?」 デイビッドは思わず、自分の論理を馬鹿げていると否定した。ジェシカは、デイビッドが勤務時間中にトイレに行って着替えるだろうと考えたのだろう。そして、そのちょっとした軽率さは、自分が許してくれる親切心からだと考えたのだろう。
デイビッドは障害者用個室に行き、そこも着替えを想定して設計されていないことにすぐに気づいた。結局、個室のドアを開けなくても、ジーンズからスラックス、Tシャツからアンダーシャツに着替えてボタンを留める方法を思いついた。前日、急いで荷造りをしてゴールデン・グースに戻った際に名札を忘れたことに気づき、またしても自分を呪った。リストにもう一つ加えるしかないな、と彼は思った。

普段なら、ニコラス・アリソンが名札を付けていない従業員に気づかないということはまずあり得ない。しかし、デイビッドにとっては残念なことに、その日は彼にとって決して普通の日ではなかった。デイビッドがデリに近づくと、アリソンは「私のオフィスへどうぞ」と言った。
数ヶ月前、アリソンは別のオフィスでデイビッドに面談していたが、アリソン個人の「オフィス」は、小学生のような小さな机と、本などが置けるオープンコンパートメントが、調理台のすぐ横にあるだけだった。アリソンの「オフィス」に呼ばれると、デリと温かい料理の両方で接客を担当していないスタッフは、調理室の入り口のすぐ後ろに立ち、中で起こっていることすべてを聞くことができた。もちろん、それはデイビッドがすでにかなり感じていた屈辱感をさらに増幅させるだけだった。デイビッドは、彼らが他の人たちの会話を聞いているのを見てきたので、彼らが会話を聞いていることを知っていたし、認めたくはないが、彼自身も時折、同じような会話を聞いていた。
ニコラス・アリソンは、小学生の椅子を思わせる椅子に腰掛け、デイビッドに一番近い椅子に座るように合図した。「ランドストロムさん」と、彼は柔らかな声でできる限りの威厳を込めて言った。「今日は話し合うべきことが山ほどあります」
デイビッドは、これから正式に手続きを取ろうとしているトラブルについて、特に心配はしていなかった。むしろ、そうなることは分かっていた。実際のところ、デイビッドの最大の懸念は、この愚痴の言い合いが一体どれくらい続くのかということだった。この時点で、20分を超えたら仕事を辞めると既に決めていた。時計を見ると1時46分。もしそれまでに会議が終わっていなければ、2時6分には退社しなければならないと心に決めていた。
ニコラスはデイビッドを見て尋ねました。「デイビッド、今日私たちが話をしなければならない理由が分かりますか?」
デイビッドはこの男から、くだらない擬似親子のような扱いを受けることになるなんて信じられなかった。「そうだね、僕たちが話さなければならない理由は分かっていると思うよ。」
ニコラスはこれ以上ないほど見下した態度でこう言った。「さて、デイビッド、なぜ私たちが話をしなければならないと思うのか、聞いてもいいかな?」
デイビッドは思わずもう一度時計を見てしまった。まだ 1:46 だった。「今日僕が遅刻したのは、これと何か関係があるのかな?」
「それは素晴らしい推測だ」ニコラスは相変わらず見下した口調で続けた。「確かに部分的には正しい。だが残念ながら、他にいくつか話し合うべきことがあるんだ」そう言うと、ニコラスは人事ファイルを取り出し、『ランドストロム、デイヴィッド・K』の欄をめくった。

デイビッドはこう提案した。「もし君が忙しいなら、どんな記事でも書いてくれるよ。もし僕を解雇したいなら、どうぞ」
ニコラスは一瞬驚いたように言った。「デイビッド、今日起こったことを考慮しても、たとえ私が本当に望んだとしても、君の雇用を解雇する十分な根拠があるとは思えない。ところで、実はそうじゃないんです。火曜日の閉店シフトまで、あなたと何か問題があったことは一度もなかったんです。」
「わかりました」とデイビッドは言った。「それはありがたいですね、どうか私にそれを渡してください。」
「ランドストロムさん、もう少々お待ちください」とニコラスは答えた。デイビッドはなぜ敬称とファーストネームを頻繁に切り替えるのか理解できなかったし、ニコラス自身もその理由を完全には理解していなかっただろう。「店の方針として、すべての記事について正式に説明し、異議申し立ての機会を提供しています。異議申し立てをされる場合は、異議申し立ての対象となった記事については店長補佐と協議しなければなりません。」
お願いだから、私は争わないで、放っておいてください!!!
もちろん、デイビッドは辛うじてそのように答えるのを我慢し、ニコラスは続けた。「まず問題なのは、火曜日の夜に作った野菜盛り合わせに、特急注文ではないのに、あらかじめスライスされた野菜を使ったことです。ご存知の通り、あらかじめスライスされたセロリの茎やブロッコリーの芯は値段が高いだけでなく、お店側も自分でスライスするよりもコストがかかります。そのため、特急注文の場合のみ、あらかじめスライスされた野菜を使うことになっています。特急注文とは、お客様が注文した時間から、お客様が注文品を受け取りたい時間帯の何時間前までにデリの営業時間を計算に入れて、2時間以内に調理しなければならない注文を指します。」
「そうだね」デイビッドはつぶやいた。「もちろん、その二つの違いは理解しているよ。」
「それにもかかわらず」とニコラス氏は答えた。「あなたは、あらかじめスライスされた野菜をスキャンしてタグ付けし、非エクスプレスの野菜トレイを作ったため、店に損失を与えました。なぜそんなことをしたのか説明できますか?」
デイビッドは答えました。「申し訳ありません。シフトの残り時間が 15 分になるまで野菜盛り合わせのことを忘れていました。水曜日の朝、皆さんが店に入ってきたらすぐに準備しておく必要があることはわかっていました。」
「この記事に異議を唱えるつもりはないということでしょうか?」
デイビッドはもう完全に苛立ちを隠せなかった。「僕はそれをしたと認めたんじゃないのか?」
「なるほど」とニコラスは難色を示した。「これは従業員ハンドブックの13ページにある『会社資産の不正使用』というステップ1の項目に該当します。これは間違いなくその範疇に当てはまります。私の解釈でよろしいでしょうか?」
「正直に言うと」と、ますます我慢の限界を迎えたデイビッドは答えた。「従業員ハンドブックを読んで理解したわけではないし、読むつもりもない。」
ニコラスはうめき声を上げた。「それと、火曜日の閉店シフトでスライサーを汚したまま放置していた。厳密に言えば、両方の出来事は同じ日に起きたので、後者をステップ2の報告書にすることもできたが、どうやらそれは私の裁量に委ねられているようだ。今日の出来事を考えると、ステップ2に早めたいところだが、今日あなたが遅くに電話してくる前に、口頭警告にすることに決めていた。そのため、口頭警告だけにする。スライサー自体はそれほどひどいものではなかったが、あなたの基準にも私の基準にも達していなかったのは確かだ。口頭警告は当然ながら正式に異議を唱えることはできないので、これで結論は出た。」
デイビッドさんはこう答えた。「野菜トレイの作業を急いで終えた後、スライサーを洗う時間がほとんど残っていなかったため、スライサーがいつもほどきれいに洗えなかったのです。」
ニコラスは反論した。「その言い訳の方が頭の中ではうまく聞こえたと言ってください。」
この時点で、デイビッドはニコラス・アリソンの戯言にもううんざりしていた。だが、もう半分くらい経ったし、時計はまだ1時51分を指していた。デイビッドはニコラスを見上げて尋ねた。「もう遅刻したか?」
「はい、承知しました」とニコラスは答えた。「本日、あなたは事前の理由なく遅刻しました。この違反については異議申し立てを歓迎しますが、異議申し立てを希望する場合はタイムカードに記録されます。遅刻の理由を正当に認めてもらうには、シフト開始の4時間前までに直属の上司である私に連絡し、遅刻の理由と出勤時刻を説明してください。私は今日10時まで出勤していなかったので、そのようなことはあり得ません。また、シフト開始の30分前を切って電話をいただいたことも記録に残しています。この記録に異議を申し立てますか?」
「いや」デイビッドはうめいた。またしても、何を根拠に反論できるのか、さっぱり分からなかった。
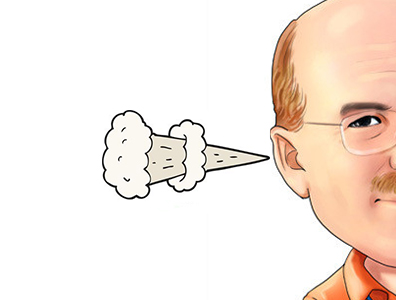
「わかりました」とニコラスは答えた。「それは出席に関するステップ1になります。出席はパフォーマンスとは全く別のカテゴリーです。パフォーマンスは、あなたのもう一つのレポートが属するカテゴリーです。もちろん、次は制服についての話に移りましょう。」
「制服だって!!!?」デイビッドは激怒した。「いいか、ニコラス。なぜ普段着だったかはもう言っただろう。出勤記録を取ったせいで、勤務時間中に着替えるのにかかった5分も会社に迷惑をかけてしまったことを謝る。会社が、たった80セントでも損をするなんて、とんでもない!」
「君の口調は本当に気に入らない」とニコラスは言った。「それに、制服違反の警告はそういう問題じゃない。どうやら名札を忘れたらしいからだ。だから、君に外見と行動の「ステップ1」を課す。これは出席や成績とは別のカテゴリーだ」
「わかった、じゃあ何でもいいよ」とデイビッドは答えた。
「しかしながら」とニコラスは続けた。「君の口調はやはり気に入らない。服はひどくシワシワだ。おそらく食料品の袋に入れて運ばれたのだろう。それに髭も剃っていない。店の基準では、男性は必ず髭を剃ることが義務付けられているが、例外として口髭は生やしていてもよい。君の髭は3日か4日でかなりきれいに生えている。そのため、外見と行動の項目でステップ2の点数をつけることにした。」
デイビッドは目を回して「ごめんなさい」と言いました。
「きっとそうだろうね」とニコラスは言った。「君の口調と、私に向かって大声を上げたという事実を考えると、不服従で書類送検されたことを後悔するべきだ。お客さんが君の声を聞き取れなかったら驚きだ。他のデリの従業員は間違いなく聞いていたはずだ。」
「おいおい、いい加減にしてくれ」とデイビッドは言い始めた。
「急げと言うな」とニコラスは言い返した。「汚れたスライサーの件で口頭注意をした時は、少し寛大な態度を取ったつもりだった。この食料品店では、指揮系統を尊重するべきだ。そして何より、規則を守らなければならない。不服従は外見と行動のステップ3に該当する。今後180日以内にこのカテゴリーでさらに注意を受けた場合は、即刻解雇する。」
「わかったよ」とデイビッドは言った。「本当にいろいろ申し訳なかった。ここ数日、本当に大変だったよ」
ニコラスは彼を見て言った。「君が短期間にこれほど多くの書類を受け取ったという事実を踏まえ、君に伝えておく必要があると思う。もし君に問題があるなら、店が後援する治療プログラムに参加すれば、仕事を失うことはない。しかし、無作為検査でクリーンでないと判明した場合は、解雇となり、店側は何もできない。その点を踏まえて、何か私に伝えたいことはありますか?」
デビッドは怒りを抑えることができず、歯を食いしばって唸り声に近い声で「俺は、薬物を、やっていない。」と言った。
「結構です」とニコラスは答えた。「最後に、仕事着に着替えるために勤務時間を使ったことを踏まえ、『勤務時間の不正使用』としてあなたに警告を発しなければなりません。もちろん、これはパフォーマンスに該当し、パフォーマンスのステップ2に該当します。この警告に異議を唱えますか?」
「いいえ」デイビッドは答えました。「私はそう思っていません。」
「お時間をいただきありがとうございます、デイビッド」とニコラスは言った。「今日はあまり気分が良くないと想像できます。それがパフォーマンスに影響するのではないかと心配しています。本日は退勤して退社し、明日午後1時に予定のシフトに戻っていただくようお願いいたします。オフィスに行ってオーバーライドを申請してください。私がシフトを終了します。」
たとえ金がかかっても、デイビッドはその日帰宅させられることに安堵感を覚えずにはいられなかった。客に逆上された瞬間、自分が何を言うか、あるいは何をするか、想像するしかなかった。ニコラスは、自分がデイビッドをさらに罰しているとは思っていなかったかもしれないが、意図的かどうかはさておき、ニコラスは残りのシフトを解雇することで、デイビッドを心から助けた。
「ありがとう、ニコラス」とデイビッドは言った。「明日は時間通りに行くよ。」「
「しっかりやってくれ」とニコラスは答えた。「明日は休みだが、今日の違反行為を踏まえて、君のために報告書をまとめなければならない。1時ちょうどに来るようにしてくれ。君が来て、報告書に署名して、その後すぐに出発したいんだ。」
「問題ありません」とデイビッドは答えた。「私はここにいます。」
____________________________________________________________________________

デイビッドは2時5分に退勤した。一日中ニコラスとやりとりしていたような気がしたが、実際には出勤時間は30分強だった。その日の給料は5ドルちょっとだった。もしかしたら、4時間勤務の給料を支払わなければならないという法律があるのかもしれないと思ったが、給与明細に実際に店にいた時間しか記載されていないのであれば、この件を追及するのはやめた方がよさそうだと判断した。
デイビッドが駐車場へ向かうと、ふらふらと歩いていると、名前を呼ぶ声が聞こえた。もしかしたら、ニコラスはダブル勤務の考えを変えて、デイビッドにタイムカードで出勤するように言ったのかもしれない。振り返ると、サミーが老人の精一杯の速さでこちらに向かって歩いてくるのが見えた。「何が起こっているんだ?」
デイビッドさんは、その日一日家に帰されたことを認めたくなかった。「ハッ!信じられないかもしれないけど、今日は仕事なんてするはずじゃなかったんだ!もちろん、残りたかったけど、家がいっぱいだったんだよ。」
サミーは疑問を抱いていました。「もしよければ、家まで送ってあげましょうか。それとも、近くに住んでいるんですか?」
デイビッドはサミーにまたタダ乗りを頼みたくなかったが、サミーはそう申し出てくれた。「正直に言うと、今日はあちこち車で走り回るのは無理だと思う。エストニア・カウンティ銀行まで連れて行ってもらえると助かるんだけど」
「今日は土曜日だよ、デイビッド」とサミーは答えた。「銀行は閉まっていると思うよ。」
デイビッドはサミーの言うことが正しかったと気づき、家まで送ってもらうことに同意した。
サミーは愛車のマーキュリー・グランドマーキスの美しさについて語り続け、デイビッドがかなり前から言っていた曲がり角をいくつか見逃してしまった。デイビッドは、サミーが自分を降ろした後、ゴールデン・グース、あるいは自宅まで、どこへ行こうとしているのか、ぼんやりと考えていた。サミーに帰り道を知っているか尋ねたかったが、失礼だと思い、代わりに黙って座り、曲がり角が近づくとだけ車が鳴るというサミーの空想に耳を傾けていた。
二人はついにデイビッドの家に到着し、サミーは道の真ん中で車を止め、デイビッドを降ろした。「おい、デイビッド」と彼は言った。「頑張ってくれよ」
「ありがとう、サミー」とデイビッドは言った。「でも、今日はカジノには戻らないよ」
"知っている。"
____________________________________________________________________________

デイビッドは裏庭に通じるドアから地下室に入り、サミーが一体どういうつもりで幸運を祈っているのか不思議に思った。サミーはデイビッドがあと一歩で解雇されるところだったなんて知るはずがない。あるいは、サミーはデイビッドが既に解雇されたと思い込んでいたのかもしれない。いずれにせよ、デイビッドが靴を脱ぎ捨て、ボタンを外した途端、二階から母親の声が聞こえた。「デイビッド・ケネディ・ランドストロム、こっちへ来なさい!」
デイビッドは、一体何の敵意なのかと思いながら、階段を急ぎ足で駆け上がった。母親は彼の存在を気遣ってくれて、地下室にほぼ家賃無料で住まわせてくれたが、叱責されることには慣れていなかった。階段を上りながら、彼は叫び返した。「どうしたんだ、ママ?」
「デイヴィ、何が問題なのかしら」と母親は椅子から立ち上がりながら答えた。「問題は、昨晩あなたがどこにいたかということよ」
「昨晩ジェシカの家に泊まっていたんだ」とデイビッドは言った。「昨日も話しただろう。僕に何か用があるなんて一言も言ってなかったよ」
母親はあざ笑った。「何かの用事であなたが必要になったとしても、私がそれを手伝うわけがないわ」あなたは今、どこに行くと言っていたかを私に話しましたが、あなたが言った場所と実際にいた場所の違いを教えていただけますか?」
デイビッドはためらいがちに床を見つめ、それから母親の顔を見て、また床に視線を落とした。自分が今どこにいるのかというだけでなく、母親が自分の居場所を知っているのかどうかも分からなかったため、この質問に答える気は全くなかった。母親が知っていることを明かすまで待つのが一番賢明な選択のように思えた。
デイビッドの母親は、デイビッドの躊躇の理由を察したようだった。「正直に答えるならそんなに難しいことじゃないと思うかもしれないけど、母親にそれを求めるのも無理があるみたいね」。彼女は部屋の中を行ったり来たり歩き、ついにデイビッドの目を見つめて言った。「ジェシカの家が、もしジェシカがいると仮定して、ゴールデン・グース・カジノの中にあるとしたら、あなたはジェシカの家にはいなかったわね」

デイビッドは、ギャンブル以外にカジノに行った正当な理由を何か見つけようと、あちこち見回した。
母親が再び彼の考えを遮った。「そんなことはしないで。最初からあなたに彼女がいるなんて疑っていたなんて、言いたくないわ。もし間違っていたら、ひどく後悔して、謝って、あなたに自分のしたことを話したでしょう。でも、昨晩、ゴールデン・グースに何度か行って、サイコロのテーブルであなたを見かけたのよ。」
デイヴィッドは、その時点で自分が完全にダメだと悟っていた。40歳も近いにもかかわらず、必ずやってくるであろう説教に耳を傾ける以外に、事実上選択肢はなかった。少なくとも、住む場所を確保し続けるためには、そうするしかなかった。
「デイヴィ」と母親は悲しげな声で言った。「ちょうど5、6年前にも同じ問題を抱えたのよ。その時は、あなたとあのギャンブルのことはもう終わりだと思っていたのに。でも、ポケットに数ドル入れた途端、またカジノに足を運ぶのね。もうずいぶん前から通っているんだろうけど、どうせ私には信じられないんだから、否定しようともしないで。たとえあなたが否定して本当のことを言っていたとしても、私には信じられへんわ」
デイビッドは何も言えなかった。まずほぼ全財産を失い、次に仕事も失いかけ、そして今、この状況と戦わなければならない。消えてしまいたいと願うばかりだったが、結局そのまま残った。母親は続けた。「辞めるのは難しいことだと思うけど、あなたは辞めたのに、どうしてまたすぐに始められたの?」
その日初めて、デイビッドはすぐに真実を告げた。「分からない。」
「いいか、デイビー。月100ドルの家賃を払えば、ここに住み続けられるって約束したんだ。もちろん、その約束に期限はない。とはいえ、君のお金は君の自由だし、どう使おうが自由だということは理解している。でも、ギャンブルに全部つぎ込んでしまうのは見たくない、というのも理解できるだろう。」
デイビッドは、このシステムを完全に実行できるだけの規律さえあれば、勝つための秘訣を偶然見つけたと確信せずにはいられなかった。しかし、母親はきっとそんなことは信じないだろう。「カジノに行ってもいいって言うの?」
「デイビー、私が言いたいのは」彼女は少し間を置いてから続けた。「あなたは何をしても自由だけど、ギャンブルに関してはあなたはダメよ。誰もがギャンブルに耐えられるわけじゃない。だから、カジノには行かない方がいいわ。そうは言っても、責任は果たさなきゃいけないわ。ええ、あなたが負っている唯一の責任はね…月100ドルの家賃を1日でも滞納したら、出て行ってもらうわ」

「分かりました、お母さん」デイビッドさんは落胆しながら答えた。「いろいろありがとう」
「ところで」と、母親は後から思いついたように言った。「エヴァンに玄関に来ないように言っておくように言ったはずよ。昨夜11時頃、エヴァンに起こされたのよ。」「
「ごめんなさい、お母さん」とデイビッドは答えた。「お母さんがそう言ってくれて、それから今まで一度も彼と話してないんだ。すぐ電話するよ」
「大丈夫よ」と母親は答えた。「今夜9時には仕事が終わるって彼に言ったでしょ。ところで、今ここで何をしているの?」
「体調が悪かったので早めに帰りました」とデビッドさんは語った。
「そして乗せてもらったの?」
「ああ、実際に誰かが僕を家まで送ってくれたんだ」とデイビッドは言った。
母親は皮肉っぽく言った。「今日は一体何がそんなに具合が悪いのかしら」。彼女は目を回し、「とにかく、エヴァンにはこれからはあなたの家のドアをノックするだけだってはっきり言ったの。いずれにせよ、あなたはカジノにいるって彼に言ったのよ。彼はそこであなたに会わなかったのね?」
「ちくしょう、母さん」とデイビッドは尋ねた。「彼に何て言ったの?」
「ええと」とデビッドのお母さんは答えました。「私が彼にあなたの居場所を教えたの。彼はあなたを探していたし、私はあなたがどこにいるか知っていたから、彼に教えたの。何か問題でもあるの?」
もちろん、問題は、デイビッドがその日聞くのは母親の講義だけではないということだった。ニコラス・アリソンの講義は含まれていない。エヴァンの講義は、デイビッドがもう話しかけないという決断をしない限り、もう聞かなければならないことをデイビッドは知っていた。心の片隅では、エヴァンがもう話しかけないという決断をしない限り、デイビッドはもうすぐ聞かなければならないと思っていた。実際、エヴァンが仕事を終えてすぐにデイビッドに会いに来ても、デイビッドは特に驚かないだろう。
「いいえ、お母さん」とデイビッドはようやく答えた。「何も問題ないよ。エヴァンに伝えてくれてありがとう。でも、彼は昨夜カジノに行かなかったから、今夜会おうと思う。」
「ところで」と彼の母親は言った。「これは介入というレベルには達していないけれど、私以外の唯一の友達に嘘をつくのはやめて。サイコロテーブルにいることはもう伝えてあるわ。」
"素晴らしい。"
____________________________________________________________________________

ある意味、デイビッドはエヴァンの携帯に電話して、昼休みにエヴァンと会おうとした。そうすれば避けられない講義を終わらせ、今日の講義を終わらせることができる。自分が自分の信念を貫き、規律正しくプレイすれば、システムが最終的に機能する理由を、自分以外には誰も理解できないだろうことは分かっていた。誰も理解してくれないことは分かっていたが、今のところは金がないし、とにかく今日を終わらせたかった。WizardofVegasにログインして、自分のシステムがうまくいったという話をでっち上げるかもしれないが、実際にはベッドに潜り込んで午前10時を待つ方がずっと可能性が高い。翌日、仕事場まで送ってもらえるかどうかもわからないので、歩くことになる可能性も覚悟しておかなければならなかった。
エヴァンは昼休みに電話をかけ、デイビッドは一発目で電話に出た。いつもの挨拶は不要だったようで、「よし、さっさと終わらせよう」と言った。
エヴァン・ブレイクの声はいつもの元気さを少し失っていた。「後で。仕事が終わったら来るよ。今夜は店が閉まったらリセットせずに帰る許可をもらってるから、あまり遅くまで起きていられないようにね。」
デイビッドさんは尋ねました。「今電話でどうですか?」
「いや」とエヴァンは答えた。「直接話したいんだ。カジノよりは君の家で話したいんだけど」
「カジノに行くのに、私の美貌はなんなんだ?」
"また後で。"
____________________________________________________________________________
予想通り、9時半頃、ドアをノックする音が聞こえた。デイビッドはすぐに返事をした。エヴァンが来るのを待っていたんだ。やっとこのつまらない一日を終わらせて、ベッドに寝られると思ったのに。

「わかりました」と彼は尋ねた。「何のためにここに来たんですか?」
「明白なことはさておき」とエヴァンは話し始めた。「僕たちが住む場所の確保についてどこまで進んでいるのかを知りたいんだ。この件で本当に一人暮らしになるのかどうか、自分で判断する必要があります。私自身、一生母と暮らすつもりはありません。別のルームメイトを探すべきか、それとも別の仕事に就いて一人で暮らすべきか、考えなければなりません。」
デイビッドは少し考えてから答えた。「なあ、何て言えばいいのか分からないんだ。今のところ、俺の所持金は12ドルくらいしかないから、一緒に住もうって言うなら、最初の月の家賃と敷金を前払いしてくれる気があるなら話は別だけど、そういう話は待たなきゃいけない。それと、君と半分ずつ出資することに完全に同意した覚えはまだないんだ。」
「そうじゃないね」とエヴァンは同意した。「でも同時に、君がそろそろ大人になって、人生らしいことを始める準備ができているんじゃないかと思っていたんだ。カジノでほぼ全てを失うことに、君が何の魅力を感じるのか、私には全く理解できないよ」
「私が負けたなんて誰が言った?」
「君はまさにそうした」とエヴァンは指摘した。「君が昨夜カジノに12ドルも持たずに行ったと私に信じさせたいのでなければね。」
「昨晩カジノには行かなかった」とデイビッドは答えた。「水曜日からずっとそこにいたんだ。行った時に持っていた金額を具体的に話す必要はないと思うが、12ドル以上は間違いなくあった」
「水曜日から起きてたの!?」
エヴァンは真剣にその質問をしたのだが、そのときデイビッドは、エヴァンが時々ちょっと間抜けなところがあるのを思い出した。「いや、僕はこの 3 晩そこに部屋を借りていたんだ。」
「まさか」とエヴァンは言いました。「部屋代を払ったなんて信じられないよ!」
「お金は払っていません」とデイビッドは指摘し、さらに「少なくとも直接は払っていません」と訂正した。
エヴァンは、デイビッドがカジノで3泊分の部屋を借りるのに必要な金額、そして実際にどれだけの金額を賭け、失ったのか、想像もつかなかった。ギャンブルについてはあまり詳しくなかったものの、デイビッドがカジノに12ドルをはるかに超える金額を持って行ったに違いないと推測できるほどには、様々な要素をうまく組み合わせることができた。
彼は首を横に振った。「デイビッド、君はもうこんなことはしないと思っていたよ。」
「私もそうは思っていませんでした」とデビッドは言った。「最初はただ無料でプレイしたかっただけだったのですが、木曜の夜に部屋を提供されたので、それを受け入れました。水曜日に銀行にいた時に、カジノのホストに電話して、予約を水曜の夜に変更しました。ここまで言っても信じてもらえないかもしれませんが、水曜の夜は正直言って何も失っていません。ギャンブルはしました。たくさん。でも、何も失っていません。」

「それは信じます」とエヴァンはきっぱりと言った。「木曜日に何が起こったんですか?」
「ええと」とデイビッドは切り出した。「木曜の夜に持ってきたお金のかなりの部分を失ったんだ。水曜日の後に持っていたお金の半分近くだったと思う。水曜日のフリープレイで少し勝ったかもしれないけど、本当に覚えていない。正直、ぼんやりしている。はっきり覚えているのは、毎晩の終わりに自分がどこにいたかだけだ。水曜日は絶対に何も失ってないってことは確かだ」
エヴァンはこう結論づけた。「水曜日にいくらか勝ったはずだ。なぜ木曜日にまた残ったんだ?」
「本当のことを知りたいなら」とデイビッドは切り出した。「ホストは私にもう一泊分の部屋とビュッフェを二つ提供してくれたんだ。金曜日にも同じことがあった。厳密に言えば今日も同じことだったが、遊ぶお金がなくて、とにかく仕事に行かなければならなかった。今日も危うくクビになりそうになったけど、なんとか自制した…大体ね。」
「どうしてそうなったのですか?」
デイビッドはニコラス・アリソンとの会話や、自分が書類で注意された理由をいくつか話した。思い出そうとしたが、正直言って全ては思い出せなかった。その話を終えると、エヴァンを見てこう言った。「ほら、部屋や食事だけの問題じゃないんだ。食事はそんなに美味しいものじゃないんだ。カジノだけが、本当に丁寧なもてなしを受けられる唯一の場所なんだ。必要なのは、少しお金を賭ける気持ちだけなんだ。」「
「レストランでチップを多めに渡して何回か行けば、スタッフがとても丁寧に対応してくれることに気づくでしょう」とエヴァンは反論した。
デイビッドも同意した。「そうだね、でもレストランに行けば必ずお金を使うことになる。カジノでは必ずしもお金を失うわけではないし、むしろ確実に勝てる方法を見つけたと思っているんだ。問題は、僕が不注意で究極のシステムから逸脱してしまったことだよ。もしそうしていなければ、そして十分な資金があれば、ほぼ確実に勝てていただろうに!」
エヴァンは尋ねた。「適正な資金はいくらですか?100万ドルですか?」
デイビッドは答えました。「いや、そんなに多くはない。100万ドルも持っている人間が、なぜギャンブルをしたいと思うんだ?」

「それが僕の言いたいことさ」とエヴァンは言った。「もし君が言うところの『適切な資金』を持っていたら、ギャンブルをする必要はない。もしギャンブルをする必要があるなら、君が言うところの『適切な資金』を持っていないということだ。どんなにお金を持っていたとしても、もっと良いことに使えるはずだ。」
「具体的な数字は言えません」とデイビッドは言った。「でも、適切な資金というのは、今の自分の資金と、ギャンブルをしたくないと思う金額の間の金額なんです。正確な数字を出すには、かなり複雑な計算をしなければなりません」
「その後どうなるんですか?」エヴァンは続けてこう尋ねた。「ギャンブルをするのに十分なお金が貯まるまで、お金を全部貯め続けるんですか? どうせやるなら、ギャンブルをする必要性を感じなくなるくらいのお金になるまで貯めたらどうですか?」
「そんなわけないよ」とデイビッドは答えた。「ギャンブルをする必要性を感じなくなるほどの金額を貯めるには計り知れない時間がかかるだろうが、ギャンブルでその金額に達するのに必要な資金を貯めるのには、それほど時間はかからないだろう。」
「あなたが「バンクロール」と呼んでいる資金の 1 ドルごとに、何ドル戻ってくると予想していますか?」
"わからない。"
エヴァンは自らの問いにこう答えた。「君は資金1ドルにつき2ドル以上の利益を望んでいるに違いない。少なくとも資金を2倍にしたいと考えているに違いない。株式市場であろうと、どんな市場であろうと、最高の投資家でさえ、そんな確実な利益は得られない。ギャンブルなら違うと思う?君と同じことを、既に誰かがやっているのではないだろうか?」
デイビッドは、自分の発言がどれほど馬鹿げているか分かっていなかった。特に、少し改良したマーチンゲール法について話しているだけだったからだ。それでも彼はこう答えた。「こんなやり方を試した人はいないと思うよ。」
「そうでもないかもしれない」とエヴァンは認めた。「だが、他の方法でやろうとした者は皆、負けたのだ。」
「私は彼らじゃない」とデイビッドは言い返した。「そして、たとえそうだったとしても、幸運が一度だけあればいいだけだ。」
「一度じゃないよ」エヴァンは反論した。
"どういう意味ですか?"
「つまり」エヴァンは眉を上げて言った。「勝つよりも負ける可能性が高いゲームで、それでも勝てば、それは幸運と言えるだろう。君がやろうとしていることを実現するには、何度も幸運に恵まれる必要がある。幸運であるだけでなく、起こるはずのことが実際には起こらないことも必要だ。それと、もし本当に幸運に恵まれたとして、どこで止めるかは決めているのか?」
「それについては考えたことがない」とデイビッドは認めた。「つまり、うまく機能するシステムがあるなら、いつ止めればいい? いつ止めればいいのか、どうやって分かるんだ? 残りの人生を過ごすのに十分なお金が貯まった時? 1年を過ごすのに十分なお金が貯まった時? 勝てるシステムがあるなら、なぜ止める必要があるんだ?」
「あなたのシステムが勝つという証拠はありますか?あなたが持っている12ドルがあなたのシステムが勝つことを証明しているのですか?」
デイビッドは我慢の限界に達していた。「エヴァン、もう言っただろ、俺が負けたのはシステムから外れたからなんだ。システムが機能しなかったからじゃない。システムは機能しているんだ。俺がミスをしてシステムから外れた。その結果、負けたんだ。」
エヴァンは天才ではなかったものの、デイビッドの立場に心理的な反論を投げかけるだけの知性は持っていた。「もしかしたら、君が言ったように、システムが負けると信じていたからこそ、システムから逸脱したのかもしれない。考えてみよう。もし君が負けている時にシステムから逃げていたなら、最終的に負けた時にシステムのせいにせずに済んだはずだ。システムではなく、規律の欠如が原因だ。システムが君を失望させたのではなく、君がシステムを失望させたのだ。」
「何と言っていいか分かりません」とデイビッドは答えた。「ただ、まさにそれが起こったことです。私はほぼ確実に勝てるシステムへの信頼を失い、いわばそのシステムに失敗、結果として全財産を失ったのです。」
「ところで」エヴァンは興味が湧いた。「全部でいくらだったの?」
「ノーコメント」とデイビッドは言った。「いいか、そろそろ寝ようかな。話をしに来てくれて本当にありがたい。でも、はっきり言うけど、明日は歩いて仕事に行くかな?」
「いいか、デイビッド」エヴァンはデイビッドの目を見つめながら言った。「僕はとてもがっかりした友達だけど、それでも君の友達だよ。12時半にここにいるよ」
「ありがとう、エヴァン、本当にそう思っているよ。」
エヴァンはデイビッドにカジノに行かないと約束させようとしたが、デイビッドはその日かなり辛い目に遭っていたので、今が厳しく叱責する時ではないと感じた。それに、エヴァンは今日した約束が嘘になるような気がした。デイビッドはしばらくカジノに持っていくようなものがないだろうし、数日待ってからデイビッドに聞いてみることにした。
____________________________________________________________________________
一方、デイビッドはどこか落ち着きを取り戻したようだった。エヴァンは親切にも20ドル貸してくれたので、給料日が来るまで仕事場で何か食べるお金ができた。さらに、デイビッドは仕事を続けることの大切さを悟り、母親のアイロンを取り出し、仕事用のシャツとスラックスにアイロンをかけた。また、できるだけ出勤時間前に髭を剃るようにした。
彼がデリに入っていくと、ニコラス・アリソンが、彼が言った通り彼を待っていた。「デイビッド、これに署名する前に、君と少し話があるんだ。」
ニコラスが自分を見ていないことを確信したデイビッドは、「ああ、キリスト」と口にした。
ニコラスが彼を見上げると、デイビッドは「もちろんだよ、どうしたんだい?」と言った。
「いいか、デイビッド」ニコラスは言った。「君は先週の火曜日までは、ここで概ね優秀な従業員だった。実のところ、このことは二人だけの秘密にしてほしいのだが、ウィルヘルム夫人との件一つとっても、君は悪くなかった…本当はもっと前に言っておくべきだったのだが、彼女は様々な組織のためにここから大量の物を発注しているので、いいように見せかけなければならなかった。次に君に会った時に、呼び寄せて伝えようと思っていたのに、忘れてしまって申し訳ない。」

「大丈夫だよ、ニコラス」デイビッドはニコラスの誠実な謝罪に感銘を受けた。「大したことじゃないんだ。本当にすっかり忘れてたよ」
「ああ、そういえば、先日彼女のためにトレイを作った時のことを思い出したんだ。もちろん、いろんな調味料の容器を全部入れるトレイだったんだけどね。正直言って、本当にひどい出来栄えだった。まるで左手の指を3本切り取られたみたいで、右利きなのに左手だけを使っていたみたいだった。あんなトレイをここから出すのは恥ずかしかったけど、仕方ないよね?」
「何もできないよ」とデイビッドは同意した。「お客さんの要望に応えないといけないけど、その日まで彼女は私にそんな要望をしたことなんてなかったんだ。」
「わかっています」とニコラスは言った。
「他に何かありましたか?」
「ああ、そうだ」とニコラスは言った。「いいか、昨日君は僕に腹を立てた。だから僕もすぐに怒り返したんだ。君を軽蔑したり敵対的な口調で接したりしたわけじゃない。でも、イライラしすぎて、本来ならすべきじゃないほどの大量の記事を君にぶつけてしまったのは事実だ。自分の判断で、昨日言ったほどの量の記事は書かないことにするよ」
"本当に!?"
「もちろんです」とニコラスは確認した。「昨日のあなたの身だしなみに関する違反、時間の不正使用も含め、全てはあなたが遅刻すると電話で伝え、ただシフトをできるだけ開始時間に近づけようとしていたという事実に帰属させます。したがって、出勤に関するステップ1は有効です。これは明らかに裁量の余地がありませんが、身だしなみに関することであなたに注意を促したりはしません。それに、あなたは今日、私よりも『規則に則って』出勤しました。もっとも、私は今日は正式には休みですが。」
「ありがとう、ニコラス」デイビッドは心から嬉しかった。「僕はおそらく、そんな恩恵を受けるに値しないと思うよ。」
「それだけじゃない」とニコラス・アリソンは続けた。「汚れたスライサーへのパフォーマンス違反は、口頭での警告だけで、実際には記録する必要もないので、これは依然として有効です。つまり、口頭で伝えられたことであり、実際に起こったことなので、取り消すことはできません。しかし、私がしようとしているのは、不服従による書面による警告ではありません。それは完全に裁量によるものですが、あなたはここで良い従業員でした。ですから、私たちが良好な労働関係を維持できるよう、少しでも努力したいと思っています。」
「感謝します。」
「そう言ってくれて嬉しいよ」とニコラスは言った。「もちろん、最初の報告書と、昨日君が時間通りに来ていれば唯一の報告書になっていたであろう『会社資産の不正使用』の報告書もだ。もちろん、これは裁量で決められるものではないので、有効にしなければならない。もし君が本当に両方に同意するなら、その報告書と出勤報告書の両方に署名してもらいたい。」
デビッドは両方の書類に自分の名前を急いで書き殴りましたが、驚いたことに、彼は自分がよく扱われていることに実際いくらか満足しており、仕事に取り掛かる気満々でした。
「最後にもう一つ」ニコラスは言った。「最後にもう一つお願いがある。」
「もちろんです」とデイビッドは断りきれない様子で言った。「何ですか?」
「従業員ハンドブックをもう1部お受け取りください。土曜日の勤務開始まで、つまり3営業日と3休日で読んでください。強制はできませんが、最初から最後まで読んでいただき、金曜日に出社して、読んだ旨を記載した書類に署名していただければ幸いです。」

「失礼な言い方ではありませんが」とデイビッドは話し始めた。「それで、あなたの要求に応じますが、なぜですか?」
「昨日の会話で、あなたは従業員ハンドブックを読んでいないと私に思わせました。オリエンテーションの後、あなたは従業員ハンドブックを読んだという書類に署名しました。あなたはハンドブックを読んでいないので、その書類への署名は虚偽です。ですから、あなたにはハンドブックを読んでもらいたいのです。」とニコラスは言った。
ハンドブックを読まなければならないというのはかなり馬鹿げたことだったが、デイビッドはその理由に反論できなかった。「オーケー、問題ありません」
「デイビッド、最後に一つだけ君に言いたいことがある」とニコラスは話し始めた。
ニコラスは、もう一人のデリ係のところへ行き、お客さんがいないのを確認すると、その日の午後に用意しなければならない野菜盛り合わせに必要な食材を買ってくるようにと、彼女を青果売り場へ行かせた。「この件でプライバシーが守られるといいんだけど…」
どうか私への愛を告白しないでほしい、とデイビッドは思った。
「デイビッド、私は一生デリのスーパーバイザーとして働くためにここにいるわけではありませんし、あなたも一生デリの店員として働くためにここにいるわけではないでしょう。とはいえ、私はいつかここでアシスタント店長になりたいと思っています。そして、その後はゼネラルマネージャーに昇進し、さらには地区マネージャーや地域マネージャーにまで昇進できるかもしれません。」もちろん、それはまだ先の話ですが、もし私が店長補佐に異動したら、誰かがここのスーパーバイザーになる必要があります。正直に言うと、あなたはかなり頭が良くて、子供っぽくない。それに、ここで働いている人の中で、その両方の資質を兼ね備えているのは、私以外ではあなただけです。ですから、清廉潔白でいられる限り、あなたが最適な選択です。分かっていただけますか?
「そうだと思います」とデイビッドは言った。
「ええ、でも、店長のアーロンが4ヶ月ほどで退職するってことは、あなたは知らないでしょうね。その仕事は欲しいですが、アシスタント店長ならまず間違いないと思うので、おそらくそちらを選ぶでしょう。その時点で、今後あなたの記録に何も追加されない限り、あなたは当然の選択肢になるはずです。『会社の資産の不正使用』については、窃盗と間違えられないように、具体的な記録を残しておきました。一度遅刻したくらいでは、そんなに悪いことではありません。私の後任が誰になるべきかについても、意見を述べたいと思っていますが、それが必ずしも保証になるわけではありませんので。」
「分かりました」とデイビッドは言った。「一言言ってくださって本当に感謝しています。」
「たぶんそうするだろう」とニコラスは考え込んだ。「だが、今は今日は休みだし、もう出発する。」
デイビッドはフロアに出て、次の客数人を元気よく対応した。ニコラスがいくら稼いでいるかは知らなかったが、きっと何らかの昇給だろうと推測した。そうすれば、俺がアルティメット・システムを運営できるだけの資金を早く貯められる、と彼は思った。
第 7 章に戻ります。
著者について
Mission146は誇り高い夫であり、二児の父です。彼は概して、多くの人が彼に抱いていた期待には遠く及ばないものの、それでも幸せでした。Mission146は現在、オハイオ州でサラリーマンとして暮らしており、ドキュメンタリー、哲学、ギャンブル談義を楽しんでいます。Mission146は報酬を得て記事を執筆します。もし彼に執筆を依頼したい場合は、WizardofVegas.comにアカウントを作成し、プライベートメッセージでリクエストを送信してください。



