このページ
究極のシステム - 第9章
概要
再出発
「大丈夫だよ」ネイト・フレイジャーはそう言った。受話器はクレードルからわずか数インチのところに、左手は切断ボタンからわずか数センチのところに浮かんでいた。「戻ってきたら電話をくれれば、何ができるか考えます。ああ、わかった。その時また話そう。わかった。じゃあね」
グレッグ、上級(そして唯一の他の)司会者は、10分間で20回目くらいに眼鏡を直し、ネイトの方を見て言いました。「あっちのトリックはどうだい?」
ネイトはうめき声を上げた。「そうだな、またデイビッド・ランドストロムに電話したんだ。それが何かの証拠か?誰も呼べないんだ!」ネイトはグレッグと二人で共有している小さなオフィスを見回し、グレッグがクロスワードパズルを解いていることに気づいた。信じられないといった様子で、「どうしてそんなに落ち着いて座っているんだ?誰も呼べないのか?」と尋ねた。
グレッグは肩をすくめた。「新年直後はいつも閑散としているよ。みんなクリスマスショッピングとか、ホリデーシーズンのパーティーに全財産をつぎ込んでしまうからね。ここは冬のリゾート地じゃないんだから。税金を払い過ぎた人が1、2ヶ月後に何人か来るかもしれないけど、お金がもらえると期待している人が一番早く確定申告をするからね。」
ネイトは状況を理解していた。実際、彼が以前働いていた別のカジノでも全く同じだったのだ。テーブルゲームのスタッフは1月中ずっと、そして2月の大半は早退していた。スーパーボウルには多少の客が集まるが、それは試合観戦中にバーカウンターのマシンをスロープレイ(あるいは全くプレイしない)する人たちがほとんどだ。州ではスポーツ賭博が合法化されていなかったため、スーパーボウルは他のまともなバーとそれほど変わらない集客力しかなかった。
「地元の人や、準地元の人に頼んでみようと思ったんだ」とネイトは考えた。「この時期に遠方から来る人はいないし、特にここではね。だから、僕たちが誰かを呼び込めば、上層部も喜ぶだろうと思ったんだ」
グレッグは眼鏡を外し、ハンカチで拭きながら言った。「地元の連中は、この時期は誰よりもお金がないことが多いんだ」と彼は言った。「少なくとも、君が電話をかけてきたことで、彼らの現在の経済状況を思い知らせることになるだろう」彼はあくびをして足を机に乗せた。「いずれにせよ、上層部はここにいても気にしないだろう。少なくとも大半は。我々が今何をしているかなんて、彼らは本当に気にしていないと思う」
ネイトはその時間で10回目くらいにオフィスを見回し、状況はもう変わらないだろうと気づいた。「それで、計画はどうするんだ?契約書に定められた給与規定を満たすために、最低限の時間だけ働くのか?」
グレッグは尋ねました。「他に何ができるんだ?ちょっと昼寝させて。それからあの小さなパッティンググリーンを出して、パットしてお金を稼げるんだ。おそらくこの場所で一番ギャンブルが盛んな場所だろうね!」
_________________________________________________________________________________

ネイトが知らなかったのは、デイビッド・ランドストロムが金欠だったわけではないということだった。むしろその逆で、彼はこれまでで一度に貯めた最高額をわずかに上回る金額をなんとか貯め、その日3度目となる3500ドル札の山を数えた。デイビッドはあと数日待てば次の小切手が届き、最低許容残高の4000ドルに達する。そうすれば、油断しているゴールデン・グース・カジノに再び「究極のシステム」をぶちまけることができるのだ。
デイビッドはWizardofOdds.comの無料ゲームで思いつく限りのあらゆるシステムを試していたが、ほとんどの試みが結局失敗に終わり、次第にフラストレーションを募らせていた。遅かれ早かれ、ほぼすべてのシステムでプレイヤーは資金を全て失うことが分かっていた。デイビッドは、自分のシステムのシミュレーションを誰かに依頼することさえ考えていた。どうやら、シミュレーションへの反対意見と、電子ゲームは不正な表現であるという認識を完全に忘れていたようだ。
数回クリックするだけで、デイビッドはまた賭けを始めましたが、結局は負けてしまいました。もしこのまま続けて負け続ければ、4,000ドルの資金では損失を補填できず、次の賭けをすることができなくなってしまいます。幸いにも、次の賭けは当たり、そのまま賭けを続けることができました。
デイビッドはついに、自分のシステムでは長期間にわたって個々のゲームに勝つことはできないと悟った。しかし、重要なのは、ベッティングシステムを取り入れながら、ゲームからゲームへと移行していくことだった。彼は、どのテーブルでも、長い勝ちや負けが時折起こるものだと気づいた。馬鹿げているように思えるが、彼らは実際にそうした。同じゲームでマーチンゲールベースのシステムを乗り切ろうとすると、そのゲームが好調か不調かの結果にプレイヤーがさらされることになる。
もちろん、デビッドは、ストリークに逆らうのではなく、ストリークに合わせて賭けるように切り替えれば、その問題に対処できると考えていましたが、そうすると、たとえばクラップスのパス ライン ベットからパスしないラインに賭けると、テーブルが時々不安定になることがよくあったようです... 最終的な結果は、プレーヤーが常に間違った側にいるということになります。
しかし、デイビッドが気づいたのは、これらの傾向はプレイヤーが常に同じゲームに固執した場合にのみ発生するということだった。彼は成功の鍵はゲームを切り替えながらプレイすることだと判断したが、それ以外は普段通りのプレイスタイルを維持するつもりだった。唯一の大きな違いは、次のゲームに進むための勝利パラメータが大幅に低下することだった。
デビッドはクラップスで次の2つのゲームに勝利し、その後フリールーレットに切り替えました。何度か負けた後、色を変えて3連勝したところで、バカラに切り替えました。その後数人のプレイヤーの結果が出ましたが(勝った場合の手数料が面倒だったので、バンカーに賭けなかった唯一のゲームでした)、すぐにクラップスに戻りました。
少なくとも、ライブカジノでプレイすれば、ちょっとした運動にはなるでしょう…
_________________________________________________________________________________
デイビッドは目の前の雪を蹴り飛ばし、塊のような雪山が空中に舞い上がり、一時的に数百の雪片へと形を変えるのを見守った。その時、突風が雪片を橋の欄干を越え、ア・ペニー・セーブド食料品店の裏道を流れる小川へと吹き飛ばした。デイビッドは橋の支柱にできた別の雪山を蹴り飛ばし、また別の突風が雪片を一つ一つ空中に散らすのを、無邪気な喜びとともに見守った。
デイビッドが嬉しかったのは、2つの理由があった。1つは2月だったので、体格がかなり大きいにもかかわらず、目的地に着く頃には汗だくにならずにあちこちを歩いて回れたこと。もう1つは、ゴールデン・グース・カジノでの3泊の滞在まであと2日だったことだ。しかし、土曜日に仕事に間に合うように、金曜日はゆっくり過ごそうと心に決めていた。

彼は自分のシステムはゲームごとに「ジャンプアラウンド」することで勝利を期待していると信じていたが、新しい戦略は勝利への積極性が少し弱まっていることに気づいた。そのため、3連休後も仕事を辞める可能性はかなり高かった。彼のスケジュールはまたもや変更され、新しい休日は火曜日、木曜日、金曜日になったが、休暇をすぐに消化してしまうため、水曜日も休むことにした。
彼は火曜日、システムに調整が必要かどうかを確認するために家にいることにした。WizardofVegas.comのフォーラムでサポートを求めたが、返ってきたのは、彼のシステムはプレイしない方がうまくいくという回答だけだった。もちろん、成功する確率や完全に負ける確率を計算しようとする人は誰もいなかった。なぜなら、ゲームを切り替える頻度と、システムのパラメータが(デイビッドが何度も説明しようとしたにもかかわらず、あまり明確ではなかった)システム自体があまりにも複雑だったからだ。
だが、とりあえず月曜日で、デイビッドには8時間のシフトが待っていた。ニコラス・アリソンが、帳簿をきちんと管理すればデリのスーパーバイザーに推薦すると約束したらしいことを、彼は改めて思い出した。そして、それ以来、帳簿はきちんと管理されている。実際、ギャンブルをしていない時のデイビッドは、まさに模範的な従業員だった。
_________________________________________________________________________________
デイビッドはデリ業界で最も面倒な注文の 1 つをこなしている最中だった。陳列されていないほぼすべての商品を 1/4 ポンドずつ欲しいという客で、もちろんチーズ以外はすべてチップスにしてほしいというのだ。デイビッドは、その注文でボロニアソーセージを削り取る必要さえありました。「削り取ったボロニアソーセージを食べる人なんているだろうか?」5分で6斤目のコールドカットソーを肉スライサーでカットする準備をしながら、彼は自問しました…

「すみません、お客様?」デイビッドは客のほうを見て、手を振っているのに気づいた。「スライサーをそろそろ掃除した方がいいんじゃないですか? 一体何種類も入れてあるじゃないですか?」
デイビッドさんはうめき声をあげてタオルを掴んだ。デリで使われるタオルはバーで使われるタオルとまったく同じものだ。「消毒剤」と書かれたバケツの水にタオルを浸し、スライサーで拭き始めた。
「お客様…」と、客は苛立たしげな声で言った。「というか、分解して掃除した方がいいんじゃないですか?妻はロンドンブロイルみたいな味のボローニャソーセージは嫌がると思いますよ。」
この時点でデイビッドは激怒の極みに達していたが、それを表に出さないようにあらゆる手段を講じていた。どういうわけか、町中の誰もがデリカテッセンやチーズを買うのに月曜日を選んでいるようだった。月曜日は食料品店業界にとって週で最も閑散としている日の一つで、しかも一年で最も閑散期とされている。もちろん、誰もいないだろうと予想されていたため、デイビッドはこのシフト中は一人でいた。
たった一人の客に、4分の1ポンドのボローニャソーセージと、その客が必ず注文するであろう他の7品を提供するために、スライサーを丸ごと分解して掃除しなければならないと思うと、本当にイライラした。スライサーはたいてい一晩に一度分解されるし、それにデイビッドは、客がサービスに時間がかかると文句を言うのは間違いないだろうと分かっていた。
デイビッドさんは尋ねました。「もう片方のスライサーを使っても大丈夫ですか?今日は全然使っていないと約束します。」
「他のスライサーはうまく動作しますか?」
幸運にも、デイビッドは顧客に背を向けていたので、顧客はデイビッドが胸に中指を立てたり、呆れたように目を回したりしているのを見ることはできなかった。「あのスライサーはこれと同じように機能しますよ。実際、あのスライサーの方が新しいですよ。」
「じゃあ、最初からあれを使わなかったのはなぜですか?」
だって、こっちの方が、俺が何かを削ったりスライスしたりして、お前らのバカに詰め込まなきゃいけない陳列ケースに近いんだもん!
その代わりに、デイビッドはこう答えました。「わかりません。これからは、まずそのスライサーを使い始める許可をもらうことにします。」
ニコラス・アリソンは、1時間後に状況を確認するためにやって来たとき、異常に怒った気分だった。怒っていたとはいえ、相変わらず几帳面だった。「ランドストロムさん」と彼は話し始めた。「あなたは1人だけなのに、なぜ肉スライサーが2台も動いているのですか?」
デビッドさんは、注文の途中でスライサーを完全に分解して洗浄するよう要求した客の状況を説明し、基本的には、客を早く帰らせたかったため、別のスライサーを使うことにしたと認めた。
「列に並んでいたのは彼だけだったのか?」
デビッドは、ひどい叱責を受けるだろうと思ったが、とにかく真実を話すことにした。「ええ、実は私たちは一日中忙しかったんです。でも、そのとき列に並んでいたのは彼だけだったんです。」
「それなら」とニコラスは切り出した。「ゆっくり時間をかけて掃除して、あの野郎を待たせ。奴がここから出て行くまでには、切ったものを50度まで温めておけよ!」
デイビッドはそのアドバイスを聞いて大笑いしました。実はそれが彼の最初のアイデアだったのです。
「でも、その間に」ニコラスは諦めたように言った。「申し訳ないけど、これの片方を掃除してもらって。一人しか使ってないのにスライサーが二つも汚れてるなんて、見苦しいしね。それに、10分後にはランチもあるしね」
ニコラスがそこにいたのは、実はデイビッドに昼食を渡すためだった。10分休憩を2回取るくらいなら、看板を出せば済むので問題ないが、昼食のために30分もデリを離れるのは難しかった。デイビッドは最初、ニコラスがなぜあの忌々しい店を掃除してくれないのかと苛立ったが、すぐにニコラスの立場に立って考えてみた。ニコラスはデイビッドの代わりをするためにそこにいた。平日はデリが2人では回らないからだ。だから、ニコラスは週に2日休みだが、その日は昼休みで、昼休みの代わりをしなければならなかった。また、自分が働いている日には、交代勤務の人の昼食も担当しなければならなかった。
もちろん、デリは週末にシフトごとに 2 人を配置するほど忙しいのですが、ニコラスにとっては、その時期の唯一の忙しい曜日である金曜日と土曜日を休むのは困難です。端的に言うと、ニコラスさんは実質的に2か月間、1日も休まず、自分の努力に対して1セントも余分に支払われることなく働くことができた。なぜなら、そのおかげで店はほんのわずかなお金しか節約できなかったからだ。

その30分間は何もしたくない、とデイビッドは思った。
デイビッドは、ニコラスが1日にどれくらい稼いでいるのか、実は気になっていたのだが、直接質問したくはなかった。ニコラスからそう聞かされていたので、もしかしたらスーパーバイザーの職に就けるかもしれないと考えて、「デリのスーパーバイザーの初任給はいくらですか?」と尋ねた。週40時間労働のデリスーパーバイザーは、他のデリ従業員と比べてわずかな給料しかもらえないことが判明した。しかし、ニコラスは週55時間近く働いているようで、時給はデリ従業員より2ドルほど少ない。それに加えて、ニコラスには「休日」を2回に分けてデリに出勤し、従業員の昼食代を払うという、今の責任もあった。
するとデイビッドの考えは、先ほどの客のことへと移った。彼はデイビッドに5つの新商品を開けさせ、8種類ほどの肉と6種類のチーズをそれぞれ1/4ポンドずつ買わせ、さらにスライサーを掃除させたのだ。兵役義務はもういい、誰もが1年間は顧客サービスを義務付けられるべきだとデイビッドは思った。
デイビッドは、長年にわたり自分が不当な扱いをしてきた接客係全員に対して、次第に罪悪感を募らせていた。社会の仕組み上、人は自分のために全てをやるわけではない。そのため、娯楽のためか必要に迫られたためか、必要なものや欲しいものを手に入れるために、外に出て他の人と接するしかない。その過程で、誰かの一日を少しでも楽にする機会が生まれる。あるいは、その人をひどく困らせ、必ずしも楽しいとは言えないプロセスをさらに惨めにする機会が生まれる。デイビッド自身、そしてデリで働くようになったデイビッドと接する人々は、あまりにも頻繁に後者の道を選んでいた。
多くの場合、自分がどれほど迷惑な存在であるかを本人は自覚していないでしょう。しかし、中には自分が何をしているのか自覚している人がいることはほぼ間違いありません。時には、顧客をただ追い払いたいだけなのに、わざと迷惑行為に走る人もいます。「毅然とした態度」を取り、そのような人に勝たせないのが賢明なように思えるかもしれませんが、結局のところ、その日の対応に耐えられないのが個人の忍耐力なのかもしれません。
デイビッドは、その日の早朝に自分で作ったサンドイッチ(ちゃんと社員ランチ料金で値札も貼ってあった)を食べながら、そんなことを考えていた。ちょうど30分後に出勤し、ニコラス・アリソンに言った。「ニコラス、残りの一日を楽しんで。こんな状態で出勤しなきゃいけないなんて、本当に申し訳ない。」
「それは最悪だ」とニコラスは同意した。「しかし、我々は皆、何かの奴隷なのだ、そうだろう?」
「君はいつか店長になれるよ」とデイビッドさんは慰めた。「そうすれば奴隷ではなくなるよ」
「安心してください、私は依然として奴隷です。ただ、よりよい報酬を得られる奴隷になるだけです。」
デイビッドは尋ねました。「その地域ではもっと鞭打ち刑が行なわれるのではないでしょうか?」
「そのことについては、あまり考えたことがなかった」とニコラスは認めた。「給料明細を開けて5分間の喜びを得るために、丸2週間も耐え忍ぶなんて、驚きじゃない? 実際、もうお金がなくなってしまって、それさえも楽しめないこともあるんだ」
_________________________________________________________________________________
デリの電話がその日初めて鳴った。店内は予約客で混んでいたものの、注文は入っていなかった。デイビッドは時計を見上げると20時14分。電話に出ようかと一瞬考えたが、ニコラスが注文を忘れていたので何か追加したいと言って電話してきたのかもしれないと気づいた。休憩時間は2回とも使ってしまったので、この日唯一の電話に出なければ、大変な目に遭うだろう。
「A Penny Saved Deliのデイビッドです。どうぞお役に立ちますか?」
「こんにちは」と中年の女性の声が聞こえた。「デイビッドさんですか?」
「有罪です」とデイビッドは答えた。「何かお探しですか?」
「あなたが来てくれて本当に嬉しいわ」と彼女は言った。「この前私たちのために作ってくれたトレイは素晴らしかったわ…」
ああ、クソッ。
「ところで、明日の午前10時からクラブのミーティングがあるんだけど、その前にトレーを受け取らないといけないんだ。サイズ3の肉とチーズのトレーが3つと、サイズ2の野菜のトレーが2つ必要なんだ。「
デイビッドは少し時間を取って、選択肢を考えた。デリは9時に開店するが、すぐにトレイを受け取りたいらしいので、朝のシフトではどうすることもできない。ニコラス・アリソンに電話して注文を伝えることも考えたが、ニコラスが休みの日に2回も来なければならないだけでも申し訳ない気持ちだった。店員に、9時までにトレイが完成するのは無理だと伝えよう。デイビッドが何らかの規則に違反しない限り、本当に無理だ…
「9時には店の奥にいますよ」とデイビッドさんは言った。「いつものように、『A Penny Saved』をご利用いただきありがとうございます」
デイビッドは肉とチーズのトレイに必要な材料をスライスし、角切りにしながらも、このまま時間通りに仕事をして優先権を得るか、時間外労働をするか、それともニコラスに電話して翌日の開店前に来なければならないと伝えるか、ずっと迷っていた。後者の選択肢は、形式的には正しいものの、デイビッドはひどく落ち込んだ。まず、休みの日に2回も来なければならず、その上、夕方に電話がかかってきて、その日の夜かシフト開始前にトレイの仕上げをしなければならないと告げられる。一体どんな人生なのだろうか?
デイビッドは、時間外労働が発覚したら即解雇される可能性もあるため、そのまま勤務時間内にとどまるのが一番だと判断した。急いで仕事をしても間に合うはずがなかったため、5枚のトレイを徹底的にきれいにし、スライサーをきちんと掃除してから、オフィスに行って許可を得ることにした。
彼は21時25分に退勤した。
_________________________________________________________________________________
「行かないでほしいよ」と、薄汚い地下室で靴紐を結んでいたデイビッドにエヴァン・ブレイクが抗議した。新しく改良されたブルー・ボネットのバター容器のパイプの水漏れからポタポタと滴る音が、背後で耳障りに聞こえる程度だった。
「いいか、君は僕を乗せるために来たんだろ?」とデイビッドは抗議した。「僕の人生のコーチ役をやるつもりじゃない。それに、もし君が望むなら、1泊か2泊してもいいよ。ベッドが2つ付いた部屋を確保できるかもしれないし、ビュッフェも手配できるかもしれない。」
デイビッドはネイト・フレイザーと良い「旅行」を交渉できたと感じていた。二人の間で少しやり取りした後、デイビッドは、そうでなければ間違いなく空室になっていたであろう部屋に3泊無料で泊まる権利と、滞在中に文字通り全く変更されることのないビュッフェ形式の食事(温め直しのみ)を1日2回無料で提供してもらう権利、そして1日20ドルの無料プレイと、その他飲食クレジットを1日20ドル分手に入れることができた。

デイビッドはゴールデン・グース・カジノで3日間の旅行を思いっきり楽しんだようだった。ネイト・フレイジャーとしては、部下がたまには来てくれるだけでも嬉しかった。3月になれば少しは状況が改善するだろうが、2月の残りは間違いなく大混乱になるだろう。実際、ネイトはグレッグの1日のスケジュールを真似し始めていた…それは、1日の半分を寝て、残りの半分をパットパットをするというものだった。
それがまた忙しくなるまで待ちきれないもう一つの理由だ、とネイトは思った。僕はこのパットゴルフで死にそうだ。
エヴァン・ブレイクは反論した。「では、どれくらい損失を出すつもりですか?」
デイビッドさんは「失うつもりはありません。ありがとうございます。勝つつもりです」と抗議した。
「結構です、ウィナーさん」とエヴァンは言い返した。「いくら持っていくんですか?」
デイビッドはちょうど35枚のカナダ紙幣と562ドル34セントの小切手をめくっていたところだった。ちょうどエヴァンがやって来た。「500ドル弱だ。銀行に預けてあるから大丈夫だ。そういえば、それを引き出さないといけないんだけど、まずはそこからでいいかな?」
エヴァンは困惑した。「給料をもらったばかりだと思っていたのに、どうやって小切手を換金したの?」
デビッドは捕まりそうになったが、まだ捕まっていなかった。「今日は小切手を受け取っていなかったんだ。」
「じゃあなんで店に行ったの?」
デイビッドさんは、店で買ったパフと歯磨き粉を掲げ、伝票を受け取った後、「いくつか必需品が必要だったんだ」と言った。「歯磨き粉は気に入らないし、パフもない。伝票のことをすっかり忘れてたよ」
エヴァンは忠実にデイビッドを銀行まで車で送り、デイビッドは小切手から62.34ドル、所持していた30.24ドル、そして35枚の100ドル札を預金した。デイビッドは新しい残高を印刷してもらい、カジノへ行くため小切手のほとんどを現金で保管していたにもかかわらず、残高が612.22ドルに増えていることに少し満足した。
二人はカジノに到着すると、デイビッドは「エヴァン、せめて中に入ってビュッフェを食べてくれよ。今日は二人とも使えないんだから」と言った。

エヴァンは同意し、二人は部屋に入ってビュッフェを食べた。その後、デイビッドは部屋にチェックインし、興奮気味にエヴァンにホテルの建物内を案内した。デイビッドの部屋はなかなか良く、キングサイズのベッド、大きな薄型テレビ、そして二人で泊まれる広さのダブルシンクのバスルームが備わっていた。「最高でしょ!」
エヴァンは感心せずに辺りを見回した。「ホテルの部屋だし、大丈夫だよ。ここからほんの数マイルしか離れてないって知ってる?」
デイビッドさんはこう答えた。「僕の地下室よりずっといいですよ、認めざるを得ませんね。」
エヴァンはため息をつきました。「地下室よりはいいけど、僕の家ほどは良くないかもしれないね。」
デイビッドは驚いて顔を上げた。「『私の家』ってどういう意味ですか?」
エヴァンは、デイビッドにアパートを借りたと言い張った。清潔で、広いキッチンとダイニングエリアがあって、バルコニーからは丘の眺めが素晴らしい。「デイビッド、いつまでも待っていられなかったから、アパートを借りたんだ。実際はかなり手頃だったんだけど、ワンルームだったから、ルームメイト探しはもう終わりだ。でも、その建物に1つか2つ空きがあるから、君を住まわせられるかもしれないよ」
デイビッドは不思議そうに彼を見た。「僕たちをルームメイトにしたいのかと思ってたんだけど?」
エヴァンは言い返した。「もし君がその計画に具体的に同意しないと言った回数につき1ドルもらえるなら、僕は敷金をタダで払えたのに。実際、僕がルームメイトになろうと提案した時は、君は一度も同意しなかった。母親の家に住んでお金を節約しすぎだって言ってたじゃないか。」
「それがまさに私の言葉だったのかどうかは分からない」とデイビッドは考え込んだ。
「ええ」とエヴァンは平然と言った。「本当にそうだったよ。お母さんが亡くなったら、君に家を残すって言ってたじゃないか」
デイビッドは、この件についてこれ以上議論する気はなかった。「少し一緒に出かけませんか?」
「ここでは何もすることはないよ」とエヴァンは言った。「良い休暇を。」
デイビッドは財布の中の4,000ドルを見つめ、休暇のことを考えた。アメリカ国内なら数日ならどこでも行けるくらいのお金はあったのに、ゴールデン・グースでその4,000ドルを何に使おうとしていたのか…よく分からなかった。それどころか、もっとカジノやゲーム、フリードリンクが楽しめるラスベガスに旅行に行った方がまだマシだったかもしれない…
「邪魔になるだけだ」。デビッドは誰にでもわかるように言った。「ラスベガスに行ったら、邪魔になるものがもっと増える。そろそろ本気で勝つことに取り組まないといけない」
しかし、そうする前に、デイビッドはひどく昼寝をしたかった。まばらなビュッフェに並んでいた料理は、ほとんどが2、3日前のものばかりで、デイビッドはすっかり満腹だった。エヴァンは「家でもっと美味しいものを作る」と言いながら、ほんの少ししか食べなかった。デイビッドは枕に頭を乗せながら、エヴァンが何をしても満足できないのはなぜだろうとぼんやり考えていた。そして、午後11時を少し回った頃に目が覚めた。
デイビッドは階下へ行く前にシャワーを浴びることにし、ゆっくりとした時間を過ごした。シャワーの水が滝のように体中に流れ落ち、髪の毛も流れ落ちていくのを感じながら、興奮が高まっていくのを感じた。厳密に睡眠時間を計る必要はなかったので、休暇はあと2日半残っていた。

シャワーから出て体を拭き、新しい服を着た。エレベーターで階下に降りると、まずは20ドルの無料プレイをどのマシンでプレイするか決めることにした。数ヶ月前にWinning Wolfのゲームを見つけた場所へ向かったが、それはなくなっていて、Buffaloか何かのゲームが置いてあった。デイビッドは辺りを見回すと、前回来た時と比べてマシンの4分の1くらいが変わっていることに気づいた。ビデオポーカーゲームだけは何年も変わっていなかった。
結局、デイビッドは Quick Hit のタイトルか別のタイトルに落ち着きました。選択できるタイトルは約 60 種類しかありませんでした。これは、タイトルとアニメーションが異なるだけで、基本的にまったく同じゲーム (フリー ゲームの仕組みも同様) である他の Bally Tech タイトルを数えなかった場合のことです。デビッドは、マシンを長時間いじり続ける必要はなく、スピンごとに最大 $1.50 を賭けることにしました。フリーゲームには出会えず、最高の結果は 3 つのクイック ヒット シンボルが 2 回出現した (これにより資金が返還されました) ことで、$5.10 を獲得しました。
デイビッドはチケットを引き換え機に持っていき、5ドル札を財布に入れた。普段は倹約家だが、お釣りは気にせず、10セント硬貨をコイントレイにそのまま入れた。彼は携帯電話を取り出し、時刻を確認すると午前0時17分だった。それからテーブルゲームコーナーへとぶらぶらと歩いて行った。
そこに着いたとき、彼は人混みがまったくなく、開いているゲームはたった 1 人のプレイヤーがプレイするブラックジャックだけだったので、当惑しました。「一体何なんだ?」彼はその質問を特に誰にも尋ねていなかったので、直接人に話す方が効果的だと判断して、ブラックジャックのテーブルに向かい、ディーラーの横を見てピット ボスに尋ねました。「ゲームはどこにありますか?」
「平日で、深夜0時を過ぎてもプレイヤーがいないんです」と彼女は答えました。「だから、他のゲームはすべて終了しました。このブラックジャックのテーブル以外は、深夜0時以降、テーブルを空けておくには各テーブルに少なくとも2人のプレイヤーが必要です。人数がそれ以下になったらすぐにテーブルを終了します。」
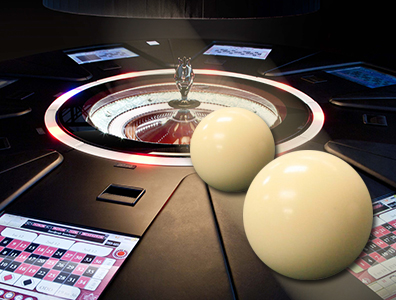
デイビッドさんはブラックジャックのテーブルを指さしながら言いました。「どうしてまだ開いているんですか?」
「あれらがあるからですよ」とピットボスは電子クラップスと電子ルーレットを指差しながら答えた。「少なくともこの州では、あれらはテーブルゲームとしてカウントされます。州によってはスロットとしてカウントされることもあります。いずれにせよ、あれらのゲームをやるなら、少なくとも一つはライブテーブルが空いていなければなりません。なぜかと聞かれたら、『本当に分かりません』と答えます」
予想通り、デイビッドも全く分かっていなかった。唯一分かっていたのは、ゲームを切り替える必要があるため、翌日まで自分のシステムを使うことができないということだった。興味深いことに、ブラックジャックは店全体で最もハウスエッジが低いゲームだったにもかかわらず、新しいシステムでうまく機能させる方法が思いつかなかったため、彼はブラックジャックだけをプレイしなかった。
_________________________________________________________________________________
30分後、デイビッドは先ほどの昼寝をひどく後悔していた。1時近くだったか、まだ1時前だったか、人によって感じ方は様々だが、デイビッドはすっかり目が覚めていて、何もすることがなかった。食事と飲み物のクレジットは覚えていたものの、ビュッフェでまだお腹がいっぱいだった。普段は酒を飲まない彼だが、バーへとぶらぶらと歩いて行った。
「ここで飲食クレジットは使えますか?」
バーテンダーはデイビッドをバカ者のように見上げて、「なぜできなかったんだ?」と言った。
デイビッドは、他のカジノでは過去にそのようなことは許可されなかったと言っていたが、実際には他のカジノで飲食クレジットを利用したことがなく、他のカジノのポリシーも分からない。デイビッドは何を頼めばいいのか分からず、「えっと…ウイスキーをいただけますか?」と尋ねた。
バーテンダーはこの時点でデイビッドが道具だと本気で思っていた。「残念ですが、もっと具体的に言ってください。」

「ジャックダニエルはいかがですか?」
デイビッドは、カジノにジャック・ダニエルが1種類しかないと確信が持てず、もし複数種類あったらどう注文すればいいのか分からず、その質問をした。そして、今度は「ロックス?」という質問が来た。
「どうだい?」デイビッドは尋ねた。「ロックしてるの? まあ、ロックしてると思うよ。」
「いやいやいや」バーテンダーは面白がりながら答えた。「氷を入れますか?」
デイビッドは少し考えてから「いいえ」と言いました。
"きちんとした?"
デイビッドにはその質問の意味が分からなかったが、バーテンダーが尋ねていたのは、ウイスキーグラスとショットグラスのどちらで飲みたいかということだった。「そうでしょうね」とデイビッドは答えた。
デイビッドさんはバーテンダーにプレイヤーズクラブカードとバウチャーを手渡しました。「わかりました。6ドルで14ドル残ります。もしくは、2杯目を半額にしてダブルにすることもできますよ」とバーテンダーは言いました。
デイビッドはダブルを一杯飲めるかどうか本当にわからなかったが、定価より半額のほうがお得だということは知っていた。「もちろん、そうしよう」
9ドルの食事代を支払った後、デイビッドは飲み物を手に入れ、一気に飲み干した。すぐにデイビッドは顔から血の気が引いて汗が噴き出し、耳から血が引くのを感じ、火を噴くのが怖くて口を開けるのが怖くなった。鼻から息を吐くと、まるで燃える炭のような感覚(と匂い)がした。ベテランの酒飲みでさえ、ストレートのウイスキーをダブルで一気に飲むのは少々気が引ける作業だ。ほとんど酒を飲まない人にとっては、痛みで叫び声を上げないようにするのも一苦労だ。
バーテンダーはデイビッドに疑わしげな視線を向けた。「ストレートにする意味って何?」
「申し訳ありません」デイビッドはやっとのことで息を切らしながら言いました。「ご質問は何ですか?」
「ウイスキーをストレートで注文する人は、たいてい少しずつ飲みたいからです」とバーテンダーは説明した。
「ああ」とデイビッドは言った。「もう一杯ダブルでもいいかな?」
バーテンダーは忠実にもう一杯、ウイスキーをダブルでストレートで注ぎ、デイビッドはそっとほんの少しだけ飲んで、「ああ、そうだね、これならずっと飲みやすいね」と言った。
バーテンダーは笑ってこう答えた。「そうだと思いますよ。」
「残ったフードクレジットをチップとして使ってもいいですか?」
「もちろんです」とバーテンダーは答えた。「ありがとうございます。書類にサインをさせていただきます」
_________________________________________________________________________________
デイビッドは徐々に酩酊状態に陥っていった。もちろん、自分が切符を買った列車がどれくらいの速さで走っているかは知らなかった。お酒を全く飲まない、あるいは滅多に飲まない人が経験する大きな問題の一つは、他人が飲んでいるのを見て、自分の耐性を過大評価し、酒が効き始めるまでの時間を過小評価してしまうことだ。
デイビッドは、自分の視界がわずかに、彼曰く「遅れている」ことに気づいた。つまり、頭を素早く動かすと、視線が視線の先を捉えるまでに数ミリ秒、ほとんど気づかないほどの時間がかかるのだ。それに加えて、デイビッドは足から少し力が抜けたような感覚を覚え、一歩一歩が少し自信を失っていた。この時点で、彼はまだ2回目のダブルスを半分しか終えていなかった。
デイビッドはそれ以外の点では気分は良く、かなり穏やかだった。目的もなくぶらぶら歩き回って1時間ほど経ったと思っていたが、飲み物を置いてスマホを見てみると、たった10分しか経っていないことに気づいた。「もういいや」と自分に言い聞かせ、もう一杯飲み干した。確かに少しヒリヒリして耳が燃え上がりそうだったが、ダブルショットを一気に飲んだ時よりは楽だった。
デビッドは、選択したテーブルゲームがどれも開いていない、少なくともライブバージョンが開いていないという事実にがっかりしましたが、まだ寝る準備ができていないと判断しました...
_________________________________________________________________________________
「500 を両替します」とディーラーは、ピット ボスのデイビッドと、先ほどのもう一人のプレイヤー、そしてディーラー自身だけがカジノのテーブル ゲーム サイドにいたにもかかわらず、いつもの声量で答えました。
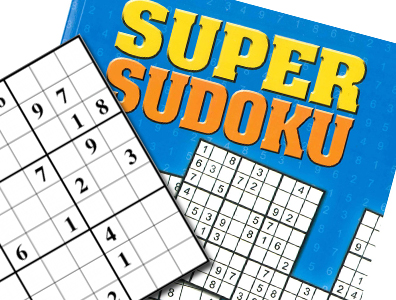
「ああ」ピットボスは言った。彼女はいつものように、この時間帯、特に空いているテーブルが一つしかない時は、形式ばった態度をほとんど取らない。実際、もしチップ制の従業員だったら、このシフトに入っていることに腹を立てていただろう。そもそもチップはすべて(ポーカーディーラーを除いて)カジノでプールされるとはいえ、ほとんどのディーラーはトークンを生み出すことで満足感を得ていた。それに、実際にプレイヤーがいることでシフトは早く進むし、ディーラーは彼女とは違って、ピットボスの席で数独の本を片手に座っているわけにはいかない。彼女は数独の本を見下ろし、その「1」が中央上部の右上隅にあることに気づき、満足した。…ピットボスとして、このシフトは悪くない、と彼女は思った。
ディーラーは再びデイビッドの緑のチップをテーブルの向こう側に送り、サイドベット用に赤か白のチップを勧めました。ディーラーはまた、デイビッドからチップをもらう唯一のチャンスは、彼の手持ちに小額のチップがいくつかある場合だと推測しました。デイビッドはまたもや拒否したため、ディーラーはチップをテーブルに出し、数秒待ってデイビッドが考えを変えるのを待ちました。そして、彼がベットするのを待ちました。
ちょうどその時、カクテルウェイトレスがテーブルに歩み寄ってきて、「お飲み物はいかがですか、それともコーヒーはいかがですか?」と声をかけた。デイビッドと、もう一人の紳士(40代前半の砂色の髪をした男性)は首を横に振り、ウェイトレスはデイビッドのウイスキーのグラスを掴んだ。
「すみません」と彼は言った。「まだ終わっていません。」「
ウェイトレスはグラスを見つめながら首を傾げた。グラスの内側にまだ少し残っている雫を見て、一体何を飲み干せばいいのか分からずにはいられなかった。いずれにせよ、空のグラスを前に彼が座っていることは、彼女にとって何の害にもならなかった。「わかったわ、私のミスよ。それを片付けたくなったら、いつでも言ってね。」

デビッドはついに、緑のチップ1枚で25ドルを賭け、ディーラーの16に対してナチュラルを配られました。ディーラーは緑1枚、赤2枚、そして「ゴールデン・グース・カジノ - $2.50」と書かれた奇妙な黄色のチップをテーブルに置きました。
デビッドは勝ち金をそのままにしておくことに決め、62.50ドルを賭けるためにすべてのチップを積み重ねました。
ディーラーは彼を見て言いました。「申し訳ありませんが、そのチップは 2 枚持っていなければ賭けることはできません。」
「それで」とデイビッドは答えた。「それで何をしたらいいんですか?」
それを吸って、ディーラーは思った。
代わりに、彼女はこう答えました。「もう一度ナチュラルが出た場合に備えて、それを保持しておくことができます。そうすれば、2 枚賭けたり、赤チップと交換したりできます。」
驚いたことに、デイビッドはディーラーが頭の中でただ彼にやろうとしていたことを実行した。「鍵をかけておくんだ」と彼は言った。「もうナチュラルは手に入らないかもしれない。」
デイビッドは次のハンドに60ドルをベットし、ディーラーが10を見せたのに対し、6と7のハンドを獲得しました。ディーラーはブラックジャックを狙っていましたが、誰もいませんでした。他のプレイヤーがヒットしてバストした後、彼女はデイビッドに手振りで「どうしますか?」と尋ねました。
デイビッドは、損をするのが正しい行動だとわかっていたので、そうしましたが、9 が出てしまい、25 ドルの損失になってしまいました。
この時点でカードは実際には少しぼやけており、デイビッドは顔を上げて、カジノの複数の色とりどりのライトが彼の目を狙っているかのように目を細めた。首を振り、テーブルに意識を戻し、次の賭けのために緑のチップを2枚置いた。
ディーラーは「幸運を祈ります、皆さん」と言い、一塁(ディーラーの左隣)のプレイヤーに7-5を配り始めた。一方、テーブルの中央に座るデイビッドは8-6を受け取った。ディーラーはエースを見せ、両プレイヤーにインシュランス(保険)をかけるか尋ねたが、二人とも断った。ディーラーはアンダーカードをちらりと見て、諦めたように肩をすくめ、キングをめくってナチュラルにし、プレイヤーのベットを回収した。
デイビッドはげっぷをして、「くそっ、まあいいか」と言った。二度目の試みで、少なくとも緑のチップを4枚立ててベッティングサークルに置いた。一塁側のもう一人のプレイヤーはディーラーに赤のチップを投げ、おやすみなさいと挨拶し、まるで後付けのようにデイビッドに「幸運を祈る」と投げかけて、その場を去った。
ディーラーはデイビッドの最初のカード、8を彼にスライドさせ、あまり良くないハンドを見せました。そして、彼女はアンダーカードを自分の方にスライドさせました。その後、デイビッドは3(今や素晴らしいハンド!)を受け取り、ディーラーは6を見せました。デイビッドが決断するまで丸1分待った後、結局テーブルには彼しかいませんでした。彼女は「どうしますか?」と尋ねました。

「この状況では、倍の努力をしなくてはならないのではないですか?」
「教科書通りです」とディーラーは言った。どうやら、先ほどサイドベットを勧めていたことを忘れていたようだ。「間違ったアドバイスはしたくありませんが、これは間違いなくダブルベットすべきタイミングです」
デビッドは緑のチップを 4 枚重ねてもう 1 つの山に並べ、もう 1 つの山の横に置きました。「よし、始めよう。」
ディーラーはプロらしくもう1枚のカードを取り出し、時間をかけすぎずにめくりましたが、早すぎず、結果は9でした。
「いいですね」デイビッドは言った。
ディーラーは何も言わなかった。ブレイクインした時、デイビッドが勝つ可能性が高いと大体分かっていたので、同意したかもしれない。経験と、バッドビートを食らったプレイヤーたちからの叱責によって、彼女はハンドが終わるまでコメントを控えることを学んだ。特にこの時、彼女が5をめくり、クイーンを出したことは、彼女にとって賢明な判断だった。普段はあまり感情を表に出さず、ほとんどのプレイヤーを心の中で心から応援するような好感の持てる人物だったため、思わず唇がわずかに歪んでしまった。
デイビッドはニヤリと笑った。「僕より君の方が心配してるよ!」しかし、デイビッドも心の中では少し心配していた。酒に酔って強がっていたにもかかわらず、ディーラーが10枚のカードを持っているのを見て、自分のシステムを動かすには4000ドルは完全に無傷でなければならないという事実がすぐに頭に浮かんだ。ブラックジャックで金を失うはずはなかった。いずれにせよ、目の前には225ドル相当のグリーンチップが9枚残っていたので、それをすべて重ねてベッティングサークルに置いた。
ディーラーはプロ意識が高すぎて何も質問できませんでしたが、頭に浮かんだのは「本当に大丈夫ですか?」という質問でした。彼女はすぐにデイビッドに2を配り、続いて8を配りましたが、彼女は9を持っていました。

「ダブルのはずだよ」デイビッドはぶつぶつ言った。
「あなたは間違っていません」とディーラーは答えました。
デイビッドは状況を少し考えた。もし負けたら、ほぼ即座に500ドルを失うことになる。この状況ではダブルダウンが正しい判断だと分かっていたが、もし低いカードが来たら、ディーラーの9に対してヒットするチャンスがあれば、もっと勝てる可能性もあった。正しいプレイをしたいと思っていたが、10分も経たないうちに500ドル以上も失うのは、本当に嫌な気分だ。財布の中を見て、残りの3500ドルを数え、ヒットの合図を出した。
ディーラーはスライドしてエースを出しました。
「クソッ!」デイビッドは叫んだ。「いい意味だけど、クソッ!」
ディーラーはさらに9をめくり、合計18枚になり、デイビッドのチップスタックは倍増して450ドルになった。デイビッドはジャックダニエルの味だけでなく、チップスタックがこんなに簡単に倍になるという期待にすっかり酔いしれていた。勝った後、彼は自分のスタックがもっと増えるはずだったことをすぐに忘れてしまった。「もし元に戻ったら、もう終わりだ」とデイビッドは宣言した。
彼はそこに緑のチップを2枚滑り出しました。
ディーラーは以前にもこのセリフを聞いたことがある。特にメモを取っていたわけではないが、ショーはプレイヤーが同じようなことを言って実際に実行する割合を10%弱と見積もっていた。もちろん、半分くらいのプレイヤーは最初からイーブンに戻らなかったが、戻ったプレイヤーのうち実際に去ったのはわずか10%だった。
ディーラーはデイビッドにナチュラルが出ることを願わずにはいられなかったが、デイビッドもディーラー自身も決断する必要はなく、彼女の10-10がデイビッドの9-8に勝利した。デイビッドはグリーンチップを6枚重ね、250ドルを目の前に残し、ベッティングサークルに置いた。

ディーラーにとってはまたしてもナチュラル。エースが出ていて、保険もなし。デイビッドだってそこまでバカじゃない。デイビッドは諦めたようにディーラーを見て、「シャッフルしてもいい?」と尋ねた。
ディーラーは「許可しない理由は見当たりませんが、ハウスポリシーではカットカードに達していないため、許可を求めなければなりません」と答えました。彼女は後ろのピットボスに視線を向け、「プレイヤーがフレッシュシャッフルを要求しています」と続けました。
デイビッドとディーラーの声は、ほとんど背景雑音と化していた。その声量から、話しかけられているのは彼女だと分かる。彼女は0から9までの数字の世界から一時的に抜け出し、顔を上げて尋ねた。「すみません、何を変えたんですか?」
「いいえ」ディーラーは、一晩中数独を解いて大金をもらえなかったことに嫉妬しながら言った。「プレイヤーがシャッフルを要求しています。」
「そうだな」ピットボスはイライラしながら尋ねた。「プレイしているのは彼だけか?」
ディーラーはもううんざりしていた。ピットボスは彼女のテーブルに目をやった。ホール全体で唯一稼働しているテーブルだ…ディーラーは彼だけがプレイしていることをはっきりと見抜いていた。苛立ちで声を荒げるのをなんとか抑えながら、「ええ、そうかもしれませんね」と言った。
「わかりました」とピットボスは結論づけた。「では、先に進んでください」
やればやるほど、やらなくてもやらで、どっちつかずの罰を受けるんだ、とディーラーは思った。そして、チップをもらえることを期待されている。シャッフルしていいか尋ねたら、ピットボスから皮肉を言われる。テーブルには自分しかいないんだから、もちろんシャッフルしていいんだから。尋ねずに、答えが「いいよ」だと分かっていながらシャッフルしたら、書類に記入される。この店はクソだ。
彼女はデイビッドに自分の敵意をぶつけるのはよくないと分かっていた。ピットボスが意地悪だったのはデイビッドのせいではなかった。たとえ彼がシャッフルを要求しても、数学的にはメリットがなかったとしても。彼女はすべてのデッキを手でシャッフルし、デイビッドにカットさせ、数枚のカードをバーンオフさせ(ハウスポリシー通り)、デイビッドに賭け金を尋ねました。
デイビッドは下を向き、残りの250ドルのチップをディーラーに差し出した。ディーラーが5に対して8-8というまたしても有利な状況に陥っていた。もちろん、スプリットする以外に選択肢はなかった。彼は500ドル札を取り出し、グリーンで返して欲しいと頼んだ。

「500を両替します」とディーラーは声を大にして言った。
「ああ」ピットボスは言った。彼女はまだデイビッドのプレイヤーズクラブカードを目の前にしていた。数独に夢中で、まだコンピューターでデイビッドのスコアを測る時間さえなかったのだ。
デイビッドはもう一枚札束を量り、適切な場所に差し込み、8枚のカードを2枚に分けた。片方の手札は15枚、もう片方の手札は合計10枚になった。15枚の手札の上に立ち、既にテーブルにお金があった彼は、ためらうことなく10枚を2倍にした。
ディーラーはデイビッドに10をめくったので、たとえ彼女が何らかの役を作ったとしても、デイビッドがダブルした手でそれを引き出す可能性はかなり高かった。ディーラーは3をめくり、合計は8になり、デイビッドは待った。
デイビッドは、ディーラーが10を出せば自分にとって良い結果になるだろうと気づいた。確かに、1つのハンドで250ドルを失うことになるので、最良の結果とは言えなかったが、ダブルハンドで勝てばデイビッドの手札は元通りになるだろう。
今回、もしこの状況から抜け出すことができたら、私は絶対にここを去るとデイビッドさんは言いました。
ディーラーがデュースをめくり、彼女の合計は10になった。デイビッドは胸から胃へと心臓が沈むのを感じた。500ドルが賭けられているこのハンドをプッシュしたらどうなるか、全く分からなかった。元の500ドルを失うことになるからだ。特定のシステムでプレイしているわけではないことは否定できなかった。だから、ぼんやりと妄想に囚われた心の中でさえ、勝てる見込みがあると信じる理由はなかった。
ディーラーはさらに 5 枚めくり、合計は 15 になりました。
デイビッドの顔が明らかに明るくなった。素早い暗算で、この時点で自分が圧倒的に有利だと分かった。エースならディーラーはもう一度ヒットしなければならない。デュース、3か4ならディーラーは15に勝ったが、20なら勝ちとなり、手札はイーブンになる。7以上はバーストする。デイビッドは5のことなど考えたくもなかったし、特に6のことなど考えたくもなかった…
ディーラーはエースを表向きにした。
「本当に待たせたいんでしょうね?」
ディーラーはデイビッドの声に緊張を感じ取らずにはいられなかった。彼女はカードを配っている間は決して自分からコメントすることはなく、ましてやコメントするために間を置くこともなかったが、中西部の基本的な礼儀正しさから、デイビッドは質問をしており、彼女は答えるべきだと考えた。「この最後のカードをめくるのにかかる時間より長くは待てませんよ。」
「そうだね」とデイビッドはすぐに答えた。「ゆっくりやってくださいよ」
ディーラーは言われた通りにカードを奥までスライドさせてから、めくり始めた。彼女は少しためらった。客の99.9999%がハンドの結果で暴力を振るうことはないと分かっていたが、全く自分のせいではない出来事で時折受けた叱責は、それでも彼女に重くのしかかり、威圧感を与えていた。デイビッドが負けたらどう反応するか、彼の様子を十分に読み取れず、ほとんど自分の意志に反して、彼女はカードをめくった…
…5です。
ディーラーは、デイビッドの両手に勝つ唯一のカードを引いた。そのカードは、デイビッドを今夜、いや、あの20分間だけでも1000ドルも貧乏にしてしまった。彼女はデイビッドに謝りたかったが、過去の謝罪がまた激しい非難を招いたことを思い出した。代わりに、彼女はデイビッドが何をしようとも、辛抱強く待つことにした。

デイビッドは30秒間、テーブルをじっと見つめていた。どういうわけか、ディーラーにとっては彼にとってよりもずっと長い時間だった。それから財布に手を伸ばし、先ほど券売機で受け取った5ドル札を取り出した。それをテーブルに放り投げ、デイビッドは落胆した様子で言った。「少なくともいい勝負はできた。鍵をかけとけ」「
「ありがとうございます」とディーラーは答えた。「幸運を祈ります」
デビッドは、最初の『バック・トゥ・ザ・フューチャー』の終わりのドク・ブラウンのセリフを思い出し、それを少し変えてみることにしました。「運?僕が行くところには、運なんて必要ないよ。」
ディーラーはそれが何を意味するのか全く分からなかったが、それが何を意味するのか理解し、思わず微笑んだ。「改めてありがとうございます!」
_________________________________________________________________________________
デイビッドはよろよろとテーブルを離れた。資金の25%を失っただけでなく、ジャック・ダニエルを4杯飲んだ余韻がまだ残っていたからだ。そう言いながら、彼はグラスを掴み、それがほとんど空になっていることに気づいていなかったのかもしれないが、カジノ内を歩き回った。
彼はグラスを手にバーに行き、「あのダブルをもう一杯ください。同じグラスでお願いします」と言った。
バーテンダーはこの要求に戸惑った。普段は、別のグラスを特別にリクエストされた場合にのみ、別のグラスに注ぐのだから、わざわざ手間をかける必要はない。いずれにせよ、彼は素早くジャックのショット2杯を取り、グラスをデイビッドに渡した。
デイビッドはそれを一口飲んで、バーから立ち去ろうとした。「すみません」とバーテンダーが声をかけた。「申し訳ございませんが、先ほどお食事とお飲み物のクレジットを全てご利用になってしまいましたね?」
「ああ、そうだ」デイビッドはぼんやりと答えた。現実に意識を戻すと、財布を取り出し、100ドル札の1枚を剥がしてバーテンダーに渡した。「90ドル返してくれ」
1ドルは決して大したチップとは言えないが、特にこんなシンプルなドリンクなら標準的な額だ。実際、バーテンダーは少し感心していた。あまりお酒を飲まない人(デイビッドもまさにそのタイプだった)は、バーテンダーにチップを渡す必要があることを知らないようだ。それに、男性はどういうわけか、他の男性にチップを渡すことに何の抵抗もないようだった。
「ありがとうございます」と彼は答えた。「ところで、バーは数分で閉まります。急かすつもりはありませんが、もし他に何か飲みたいなら、そのグラスを空にするか、また来た時にそのグラスが見えないようにしていただく必要があります」それからバーテンダーはデイビッドにウインクした。
デイビッドは首を横に振り、「いいよ」というより「いいよ」と答えた。
_________________________________________________________________________________
デイビッドはジャックをそっと口に含みながらカジノを歩き回った。一口ずつ飲むたびに、何か即効性があるか試していたが、もちろんアルコールはそうはいかない。デイビッドは今や2,990ドルを手にしていたが、銀行に少しだけ貯金があることに気づいた。そのお金は絶対に必要ないと考えたが、あると安心した。

彼はブラックジャックのテーブルに戻り、次のセッションで何かできることはないかと考えた。巻き返したいという気持ち以外に、ディーラーが本当に気に入っていた。しかし、冷静な脳が支配権を握り、ブラックジャックに戻るなんて考えもせず、きっぱりと「だめだ」と叫んだ。現金で飲み物を買っただけでも十分ひどいのに。残りのお金は、翌日の夕方、あるいは午後にプレイする「アルティメット・システム」のために取っておかなければならなかった。
同時に、彼は1,000ドルを取り戻したいという思いと、それを実現する手段がないことに無力感を覚えていた。最終的に、スロットマシンで幸運を掴もうと決心し、5つのラインにそれぞれ3ドルずつ賭ける、合計15ドルのクイックヒットのゲームを見つけた。
デイビッドは何が自分にそうさせるのか全く分からなかったが、プログレッシブ最高賞金99,155.12ドルを見ると、自分が当たると確信せずにはいられなかった。アルコールはすぐには効かないかもしれないが、速効性はあり得る。デイビッドはグラスに残っていた酒を一気に飲み干し、1、2分も経たないうちにその効果を実感した。
デイビッドは、自分の100ドル札のうち1枚を機械に通すのに四苦八苦した。あまりの苦労に、部屋に戻ってもう終わりにしようかと思ったほどだった。そもそも、スロットマシンで1000ドル札を回収できる見込みなんてあるのだろうか?
_________________________________________________________________________________
やがて、デイビッドは自分が何かをしているというより、むしろ上から見ているように感じ始めた。信じられないことに、デイビッドは持っていた29枚の100ドル札と4枚の20ドル札、そして10ドル札を全て取り出し、1回15ドルという最高額の賭け金で回転するマシンに投入した。彼は、クレジットがかなり急速に減っているにもかかわらず、スロット ポイントが急上昇するのを見守っていました。
デイビッドはある時点で約1300ドルを失い、それでもフリーゲームに一度も出会えなかった。彼は急速に冷静さを失い、マシンを拳で叩きつけないように全力を尽くした。彼を落ち着かせたのは、部品の一つを交換するのにどれほどの費用がかかるか、そしておそらくカジノから永久に追い出されるだろうという事実に気づいたことだけだった。
しかし、空想するのは悪いことではなく、少なくとも賭けた金額に比べて負けたり、非常に小さな勝ちが続いたスピンのあと、デビッドはついにフリーゲームのセットを獲得しましたが、1,700ドルの損失でした。
デイビッドは、まるで自分の選択が数学的な影響を与えるかのように、提示されたボックスからゆっくりと選び始めた。しかし、選んだ4つのボックスのうち3つだけで、20回のフリーゲーム、20回のフリーゲーム、そしてワイルド+5回のフリーゲームで25回のフリーゲームと3倍のマルチプライヤーを選んだ彼を、それらの選択が重要ではないと納得させることは難しかっただろう。

残念ながら、デイビッドはボーナスの再トリガーを獲得できず、最も大きな勝利はクイックヒットシンボル5つで、マルチプライヤーを考慮すると450ドルの払い戻しとなりました。結局、フリーゲームの合計は約800ドルとなり、デイビッドは依然として900ドルの損失を被りました。
なぜこれをプレイしているのでしょうか?
デイビッドは一体何が自分をゲームを続けさせているのか、全く理解できなかった。マシンに賭けた金額はたった2000ドル強で、自信につながるような出来事は全く起きていなかった。それでもデイビッドはゲームを続けた。
その後1時間、デイビッドは5回と10回のフリーゲームを獲得しましたが、どちらのフリーゲームも結局は何も得られませんでした。最終的にクイックヒット・プログレッシブ6回で$910.05を獲得しましたが、その時点でマシンに残っていたのは$1517.05だけでした。
多くのプレイヤーにとって、この結果は祝うに値するものであったにもかかわらず、デビッドはこの時点で、マシンに残っていた金額のほぼ全額がまだ失われているという事実に苛立ちを感じました。
彼は、まるで機械が自分の決意の度合いを気にするかのように歯を食いしばり、回り続けた。
クイックヒットマシンで負け続けるにつれ、彼の行動と思考はますます不安定になっていった。何の理由もなく、彼はウイスキーグラスを掴み、近くのゴミ箱に放り投げた。マシンにぶつかって割れようが床に落ちようが、ほとんど気にしなかった。驚くべきことに、デイビッドの運動能力のなさを考えると、ウイスキーグラスはゴミ箱にきれいに落ちた。
さらに30分後、汗だくになったデイビッドは、チケット代が700ドルしか残っていないことに気づき、真剣にもうそこで終わりにしようと考えていた。
このまま続けるなら入院しなくてはならない、と彼は思った。
それでもデイビッドは、まるで完全に制御不能になったかのように、ゲームを続けた。リズミカルにボタンを叩くと、すぐに「スラムストップ」状態になった。つまり、スピンのグラフィック表示を機械にさせず、結果に直行したのだ。
デイビッドはフリーゲームに当たったと思った。「チーン、チーン、チーン」と鳴ったが、最後の「チーン」はクイックヒットシンボルが1つ以上出現したことを示す音だった。ひどく嫌悪感を抱いたデイビッドは、マシンに残っている金額を確認するために、少し下と右に視線を向けた。212.05ドル。
デビッドはその時、どうしたらいいのか全く分からなかった。もしできるなら、5つのラインそれぞれに1ラインあたり42.41ドルを賭けて、とにかく早く終わらせたかった。結局、マシンをスラムストップするのを諦め、結果がどうなるか様子を見ることにした。3000ドル近くも現金でマシンに賭けたのに、500ドル以上の当たりがたった2回しか出ず、こんなに早く負けてしまうのは、本当に辛かった。次の3回のスピンも完全に負けてしまった。
マシンに167.05ドル残っていたデイビッドは、スピンの合間に5、6秒間完全に止まった。ここ数時間で失った金額に吐き気がした。実際、吐き気を催しそうになったほどだった。しかし、何よりも彼を苛立たせたのは、銀行の預金がどうにかならないかぎり、あと数ヶ月はギャンブルができなくなるという考えだった。
「そんなこと全部」と彼は心の中で言った。「しかも、私はそのシステムを使ったことすら一度もない。」「
次の回転で彼はすぐに頭を上げました。

ディン
クイックヒットシンボル、最初のリール!
チン、もう少し大きくして…
あと2つ、2番目のリール。
チンッ!!!
あと3つで、3番目のリールもカバーできました!
チンッ!!!
そんなことはあり得ない、でも実際に起こっていた!あれだけの心配と不安を抱え、マシンに3,000ドル近く、そしてその夜に4,000ドルも失った後、デイビッドはついにクイックヒットシンボルを少なくとも8つ獲得した…
少なくとも、待って?
リールの回転時間は普段と変わらないのに、ものすごく長い時間回転し続けました…
チンッ!!!!!!
あちこちでベルとサイレンが鳴り響き、マシンはデイビッドも知らなかった色を点滅させ、マシンは 9 回のクイック ヒットと 99,155.12 ドルのジャックポットを獲得しました。
この夜、デイビッドはシステムを必要としていなかった。スロットマシンで遊んでいただけで、すっかり酔っ払っていたのだ! デイビッドは飛び上がって目を閉じ、全てを飲み込んだ…
第 8 章に戻ります。
著者について
Mission146は誇り高い夫であり、二児の父です。彼は概して、多くの人が彼に抱いていた期待には遠く及ばないものの、それでも幸せでした。Mission146は現在、オハイオ州でサラリーマンとして暮らしており、ドキュメンタリー、哲学、ギャンブル談義を楽しんでいます。Mission146は報酬を得て記事を執筆します。もし彼に執筆を依頼したい場合は、WizardofVegas.comにアカウントを作成し、プライベートメッセージでリクエストを送信してください。



